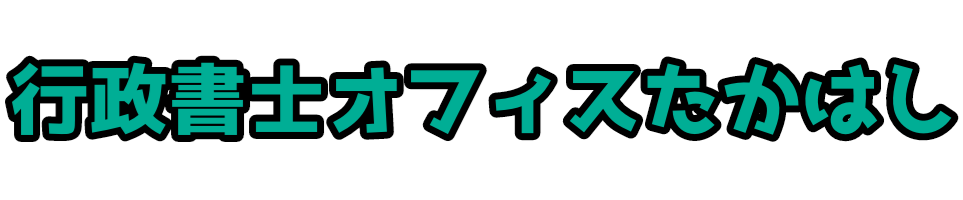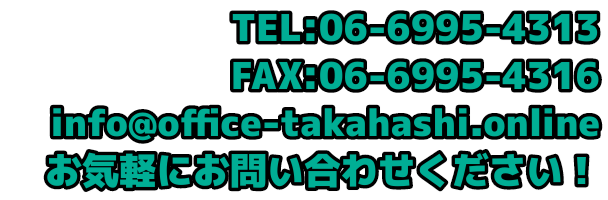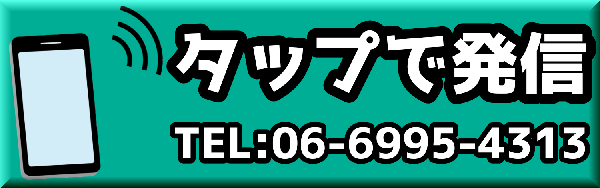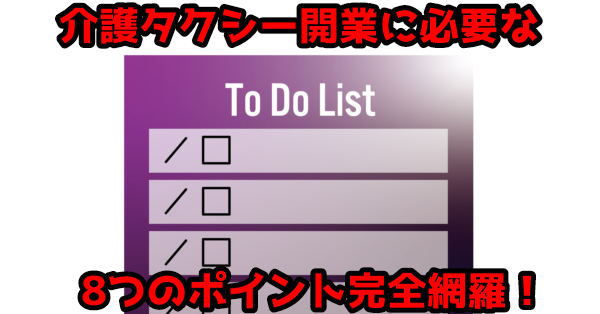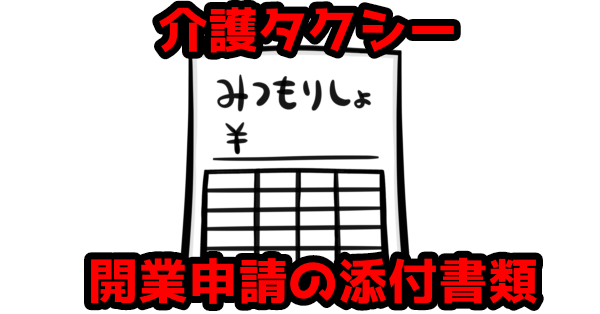そろそろ事業所の事業を拡大したい、しかし「人手不足だ」「募集しても来ない」等で断念していませんか?
その場合「介護タクシー(福祉タクシー)事業」を検討されてみてはいかがでしょうか。
実は介護タクシー事業は
- 障害福祉事業と相乗効果が高い
- 少ない人手で開業できる
- 他社との人の取り合いとは別の所からの人材を引っ張って来れる
- というメリットで開業が出来ます。
この記事を最後まで読んでいただくと「障害福祉事業と介護タクシーの相乗効果の高さ」「障害福祉を行っている事業者が介護タクシーを開業するメリット」等がわかります。
介護タクシー(福祉タクシー)の開業を専門とする行政書士が、障害福祉事業と介護タクシーの相乗効果について徹底解説させて頂きます。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
障害福祉事業の事業拡大として介護タクシー
不動産会社や警備会社、保険会社等が介護事業、その延長で障害福祉事業にも進出してきています。
ですが障害福祉事業から他事業進出はなかなかありません。ですが同業種で事業拡大を計画しても人員確保が大変です。では少人数立ち上げ可能、近接異業種があるとしたらどうでしょう。
他業種進出の場合、どうせなら相乗効果が見込める事業の方が良いです。介護タクシーは旅客運送業ですが下記のような相乗効果があります。
- 居宅介護のノウハウを活かせる
- 利用者をそのまま顧客に変えられる
- 事業拡大とサービス拡大が一度に出来る
- 同業他社の仕事も請け負える
- 資金繰りが良くなる
資格保持者の求人のしやすさについては
二種免許 :令和4年時点で158万人(警察庁・運転免許統計より)
介護福祉士:令和3年時点で181万人(法務省のHPより)
となります。おどろく事に介護福祉士の方が多いのですが、受験資格がある人で考えると二種免許の方が圧倒的に多い事が伺えます。
介護タクシーは即金、資金繰りの良化にプラス
障害福祉事業については、国保連からの支払がおおよそ2.5ヶ月後と言われています。
支払いが遅い=資金繰りが厳しい時も増えるとういことです。ですが事業拡大として介護タクシーを始めることによって
- うち何十万かでも即金でもらえる
- カード払を導入しても翌月には入金
となりますので、資金繰りの悪い月について、全て国保連での売上の場合より良化します。
異業種進出を考えたい、介護人材の取り合いに限界を感じている場合、介護タクシーの開業を検討をお勧めします。
弊所は介護タクシー開業のための運輸局の許可、申請書作成の代行、事業支援も行っています。事業について詳しくは下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEでのご相談は無料です
介護タクシーは有償で利用者を運べる運送業
白ナンバーの施設送迎車では利用者を病院へ運べません。
「無償ならいいでしょう?」という発想に至りますが、無償でも違法という判例が出てしまいました。裁判所曰く「そこだけ無償というのは認められない」とのことです。
施設送迎車が合法な範囲は
- 施設←→自宅を無償
のみで
- 施設←→自宅を有償
- 施設←→病院を有償・無償
- 自宅←→病院を有償・無償
上記は全て違法となります。これをやりたい場合は、緑ナンバーが必要になります。
障害福祉事業の利用者は9割以上病院を利用している
要支援、要介護に認定されている利用者は、9割以上が通院などしています。通院していない方が少数となります。
- 訪問先の利用者が病院に行きたい
- 施設の利用者が病院に行きたい
となると、外部の業者に頼む必要があります。
介護タクシーの事業者が圧倒的に足りていない
介護タクシーの数は現状全く足りていません。
予約がいっぱいでかなり先まで予約が取れないという話は、障害福祉事業を経営されているなら肌で感じていると思います。
外部の業者に頼もうにも業者が居ないのが現実です。
となると以下の発想に至ったことが一回でもあるのではないでしょうか。
- 自社で一台だけでも確保すればかなり助かる
- 施設送迎車うち1台を緑ナンバーに出来れば
そしてその直後に
- 緑ナンバーって簡単に取れる?
- お金かかる?
- 資格が必要なの?
- 1台からでも取れるの?
- 採算取れるの?
調べて見るも複雑すぎて実行にうつしずらいという事ではないでしょうか。
上記の回答については、すべてYESと答えることが出来ます。
緑ナンバーが、比較的容易に安価で取れるとしたらどうでしょうか。一つ言える事は、障害福祉事業で比較的許可と資金の難易度が低い居宅介護事業よりは簡単だと言うことです。
尚、現状の介護タクシー市場については下記の記事をご覧ください。
尚、介護タクシー市場の現状、事業を始めた場合の収支の目安等の更に詳細を知りたい、運輸局への許可を取ってほしい場合は、下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEでのご相談は無料です
介護タクシーと相乗効果の高い障害福祉事業
居宅介護
居宅介護は、利用者が自宅に居るのであまり介護タクシーの出番が無いというイメージがあるのですが、実はそうではありません。
訪問介護は専門支援相談員の立てる支援計画で、通院をします。居宅介護の利用者は9割以上通院しています。
これを外部の介護タクシー事業者に頼むと
- 運賃部分が安く出来ない(タクシー料金に準ずる)
- ヘルパーさんが同乗出来ない(原付きで追いかける等の例がある)
等かなり面倒になり、利用者様に寄与出来ると言えません。
これを自社で介護タクシーを持つと
- 運賃部分に支援計画内送迎の料金を設定出来る
- ヘルパーさんの自家用車で送迎することも出来る(追加許可必要)
となり、利用者様もかなり利便性が高くなります。
居宅介護のサービス向上及び、事業拡大の一環として介護タクシーを検討してみては如何でしょうか。
デイサービス
通所介護の場合正直な所、居宅介護ほど相乗効果が高いとは言えませんが、下記のような事が期待出来ます。
- 施設送迎車を1台でも、緑ナンバーに変えると売上を生み出せる
- 利用者を川上で顧客化出来る
- 介護や乗降介助のノウハウは持っている
通所介護については、施設の送迎車が施設←→自宅を送迎しています。
ただ、もし施設利用者が自宅から病院へ通院したいとなった場合、自社にタクシーがあると案内をしてあげられます。
既に施設送迎車を何台か持っているパターンが多く、乗降介助のノウハウも蓄積されています。うち1台を緑ナンバーに変えるだけで、売上が生み出せるシステムに変わります。
顧客のライフタイムバリュー(顧客生涯売上)を上げることが可能です。
介護施設
前述しましたが、介護施設の場合
施設←→自宅
の送迎しか出来ません。そして、施設利用者のほとんどは通院をしているはずです。
勿論、通院以外の外出もあります。買い物、外食、旅行等もあるかもしれません。
これらの需要を満たすには、緑ナンバーが必要です。
外部の業者だけではこの需要が満たせない場合
- 自社の施設送迎車を1台緑ナンバーに変える
- 施設の空いている土地に福祉自動車を1台導入する
上記のことが検討出来るのではないでしょうか。
障害福祉事業と介護タクシーの相乗効果、御社に適した開業の形などの提案をしてほしい。運輸局へ許可を取ってほしいという場合、下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEでのご相談は無料です
障害福祉事業者と介護タクシーの許可を同時に取ると特典がある
介護タクシーの開業はバリアフリーや障害者福祉の観点から国も推奨しています。
そして、障害福祉事業者と介護タクシー(運送業)の許可を同時に持っていると、下記の特典が受けられます。
- 利用者を病院へ有償で送迎出来る
- 通院等乗降介助に介護保険が適用できる
- 白ナンバーで有償運送できる(通称ぶら下がり許可)
- 介護タクシーと障害福祉事業の事務所を兼用に出来る
- 運行管理者が兼任できる
- 条件が揃えば1人増員・1台で始められる
詳細は下記です。
利用者を病院へ有償で送迎出来る
無償なら白ナンバーでも利用者を病院に運べるのかという事ですが「病院の送迎だけ無償だというのは認められない」という判例が下りましたので、無償でも出来ません。
つまり、利用者を自宅←→病院へ運送する事それ自体に緑ナンバーが必要になります。
まずはこれが可能になることで、利用者も依頼先が一箇所にまとまり、利便性が上がります。
通院等乗降介助が国保連に請求できる
「介護タクシーの利用料金を国保連に請求できる?」という疑問を頂くことがあります。
介護保険を介護タクシーに適用したい場合、障害福祉事業所と介護タクシーの許可を両方持っていないと国保連に請求ができません。
介護タクシーは運送業許可だけで営業が出来ますが、国保連に請求を出来る指定がないと、支援計画に含めることが出来ません。
上記の条件により、国保連に請求ができる介護タクシーは現在かなり少ないです。
これが適用出来るとなると、これだけで他社との差別化になります。
白ナンバーで有償運送できる(通称ぶら下がり許可)
介護タクシーと障害福祉事業所の両方の許可を持っていると
・自家用自動車有償運送
という許可を付随で取ることが出来ます。
これは、利用者が支援計画に含まれている通院について、ヘルパーさんが自家用車で病院へ送迎する事が出来ます。
外部の介護タクシー業者に頼み、ヘルパーさんがタクシーを追いかけていって乗降介助という面倒な展開も無くなります。
尚、白ナンバーのヘルパーさん運送について詳しくは下記の記事も御覧ください。尚、介護事業となっていますが障害福祉事業所でも全く同じ恩恵が受けられます。
【事業者必見】介護タクシー&介護事業で白ナンバー有償運送が可能に
白ナンバー有償運送(ぶら下がり許可)の輸送の範囲
介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む。)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。
介護タクシーと障害福祉事業の事務所を兼用に出来る
続いて経営面の話です。
新しい事業を始めるとなると、新しい営業所を借りる等初期費用がかかります。
しかし、すでに障害福祉事業所を運営している会社が、さらに介護タクシーを開業しようとする場合、障害福祉事業所の事務所を介護タクシーの兼用営業所に出来ます。
障害福祉事業と同じく、介護タクシーも運送業で国の許可を必要とする事業なのですが、ここは兼用事務所でも許可が下ります。
最小1人の増員で開業できる
大阪及び近畿2府4県で介護タクシーを開業する場合は、最少人数が2人となります。
- 運転手
- 運行管理者
の2名です。運行管理者は、運転手を管理する役なので、この2役は兼任が出来ません。
ただ、運転手との兼任が出来ないだけで、障害福祉事業者の既存の事務管理の方は運行管理者と兼任する事が出来ます。
つまり、最小でニ種免許保持者1人雇い入れると介護タクシーの人員要件は足りてしまうことになります。
条件が揃えば1人増員・1台で始められます。ミニマム開業出来るのがこの事業の長所であります。
尚、1台とは言わず2,3台で始めたいという場合でも、どの様な開業の形が良いかを提案させて頂きます。下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEでのご相談は無料です
介護タクシー開業のデメリット・注意点
メリットは沢山ありますが、当然デメリットもあります。これらをメリットが上回れば、是非開業を検討してみて下さい。
初期コストがかかる
初期コストは弊所が関与した事業者様だと300万~600万の例が多いです。
この差額については、車を一括または分割購入するか、リースにするかの違いになります。
車をリースにして、土地や営業所を自社の既存の物にすることで、200万を切る例もあります。
ただし、初期コストを抑えると、ランニングコストが上がるので、事業形態に合った開業の形を検討したいです。
加えて運輸局の決まりにより、これについては
- 1年分の任意保険(約20万)
- 2ヶ月分2人分の人件費(約90万)
等が含まれているので、実際の出費となる額はもう少し下がります。
尚、開業資金についての詳細は下記の記事もご覧ください。
ニ種免許保持者を探すのが大変
これが一番大変ですが、ニ種免許保持者を見つければ、殆どの課題はクリアー出来たも同然です。
方法としては
- ニ種免許保持者を募集する
- 既存の従業員の方にニ種免許を取得してもらう
もし取得して貰う場合、予算としては合宿25万、通いで40万程度見ておいてください。
現在ニ種免許保持者の求人については25万程度での募集が多いです。
社会保険負担分も見て、30万程度の人件費がかかると考えておく必要があります。
尚、二種免許の取得についての詳細は、下記の記事もご覧ください。
【事業主必見】介護タクシー法改正情報│最短19歳で2種免許が取得可能
デメリットは克服できればメリットが上回ります。御社に適した事業形態を提案させて頂きます。まずは下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEでのご相談は無料です
介護タクシーのランニングコストと売上
介護タクシーのランニングコストは大体300万~400万程度の例が多いです。
ただし、これは介護タクシーを全く別事業として行った場合です。
実際は既存で障害福祉事業も行っていると思いますので、介護タクシーの依頼がない場合は内勤作業等を行うことで人件費は押し並べられる事になります。
介護タクシーの売上は、軌道に乗れば1台辺り月30万~50万。年間で360万~600万程度が見込めます。
すでに利用者が何人も居る状態の場合は、初期からある程度の売上を見込めるでしょう。
介護タクシーは足りていないので、同業の障害福祉事業者からの仕事も受けることが出来ると月30程度の基本売上には結構早くたどり着けると思います。
尚、介護タクシーを開業した時の収支について詳しくは下記の記事も御覧ください。
【開業志望必見】介護タクシーの平均的な収支はこうなる!法人編
最速で介護タクシーを開業する方法を解説
まずは簡単に介護タクシーを開業するには何をを集めればいいかを解説します。詳細については詳細記事をご覧下さい。
介護タクシーに必要な人員
介護タクシーを始める最少人数
最少人数は2人です。
ただし、障害福祉事業所がサイドビジネスとして始める場合は、1人が兼任可能ですので、実質運転手を1人雇えば事足ります。
介護タクシーに必要な資格
ニ種免許が必要になります。
介護タクシーは、おそらく殆どの事業者の方がリフトやスロープ付きの福祉自動車で始めると思います。
その場合、介護タクシーについては、居宅介護職員初任者研修(旧:居宅介護従業者研修2級課程)の障害福祉系の資格は必須ではありません。努力目標となります。
【開業前必見】介護タクシー開業や運営に必要な資格リスト
【開業前必見】介護タクシー運営に必要な8つの資格の取得方法リスト
介護タクシーに必要な設備
営業車
通常の乗用車でも始められますが、その場合は障害福祉系資格が必須になります。
リフトやスロープ付きの福祉自動車で始める場合は、居宅介護職員初任者研修(旧:居宅介護従業者研修2級課程)の資格は努力目標になります。業務を行いながらの取得でも問題ありません。
尚、障害福祉事業+介護タクシーという形でも、高齢者介護の資格「介護職員初任者研修」等でも問題ないとされています。
営業所
特に厳しい条件はありません。常識的な広さがあればよく、現在の障害福祉事業所と兼用事務所も可能です。
最低、介護タクシー事業用のデスク1つと専用のパソコンとプリンター1台ずつくらい用意してあれば、許可が下りないという事はありません。
【開業前必見】介護タクシー「営業所」の物件。選び方・許可の要件
休憩所
運送業でのすで、ドライバーの休憩所が必要です。すでにヘルパーさんの休憩所がある場合は兼用出来ます。
ない場合は、事務所の一角をパーテーション等で仕切り、ソファなどを置くことでも休憩所として認められます。
【開業前必見】介護タクシーに必要な「休憩所」を簡単に確保する方法
車庫
車庫については規制が緩和され、至って普通の駐車場でも許可が取りやすくなりました。
- 営業車の全長全幅より広い
- 洗車用の水道
これらが必要です。
水道がない場合は、近隣のガソリンスタンドで水道を借りる事でも許可が下ります。ガソリンスタンドのオーナーから一筆頂く必要があります。
介護タクシーの開業に必要な資金
許可を取るためだけに必要な預金残高は200万~500万程度となります。
開業のためには、運輸局に残高証明をチェックされます。
開業には300万~600万と先述しましたが、許可だけに必要な残高はここからマイナス100万で大丈夫です。
ミニマム開業であれば200万切る例もあります。
【記入例】介護タクシー開業申請書「資金計画」を専門家が徹底解説
障害福祉事業に加え介護タクシーを始める手続きが解らない時は
ここまでお読みいただき、特に諦める要素が無く
- すでに障害福祉事業を運営している
- 事業を拡大したい
- 他業種にも手を広げたい
- 他業種なのでやり方がわからない
というお考えが揺るがない場合は、介護タクシー開業専門行政書士である弊所にご相談下さい。
介護タクシーの事業の説明、御社に適した開業形態をご提案させて頂き、運輸局の許可の代行までワンストップで承ります。
介護のことはわかるけど、運送業のことはわからないということであればぜひ弊所まで、下記メールフォーム、LINE、お電話等で「初回無料相談希望」と明記下さい。弊所より連絡させて頂きます。

介護タクシー関連事業
下記のような事業を紹介しています。良ければご覧くださし。
まとめ
- 居宅介護事業所の指定と、介護タクシーの営業許可を同時に取ると相乗効果が高い
- 国保連への請求、白ナンバー運送、病院への送迎等の特典が受けられる
- 2人1台というミニマムなスタートで事業が拡大出来る。
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。
LINEでのご相談は無料です
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。
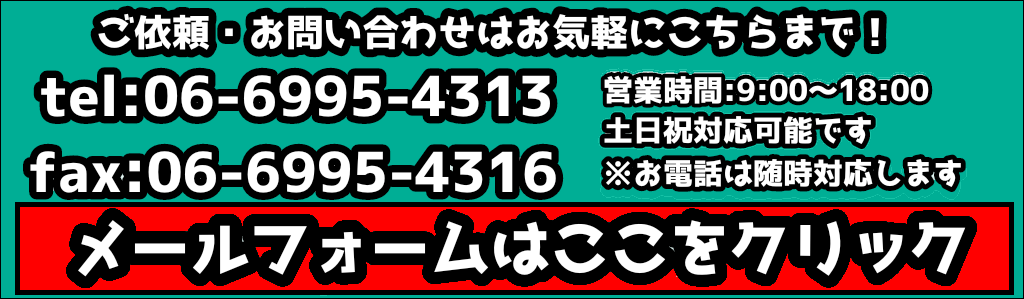
メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)