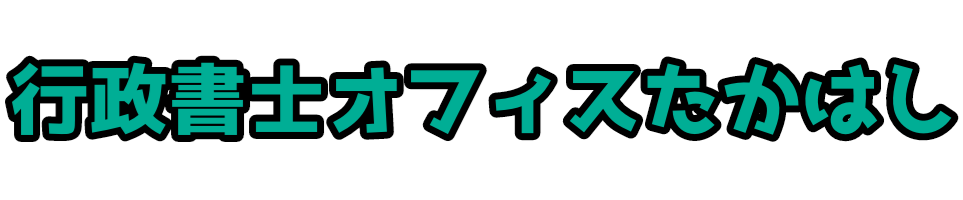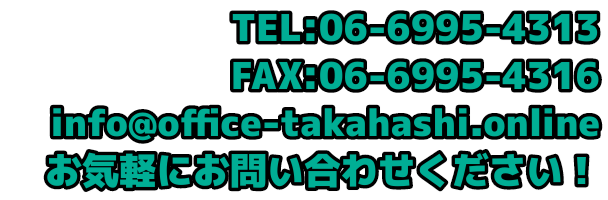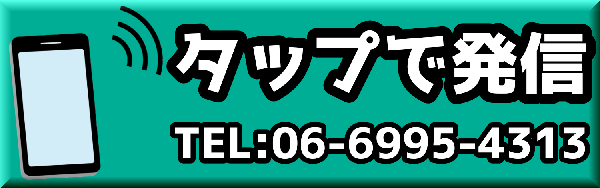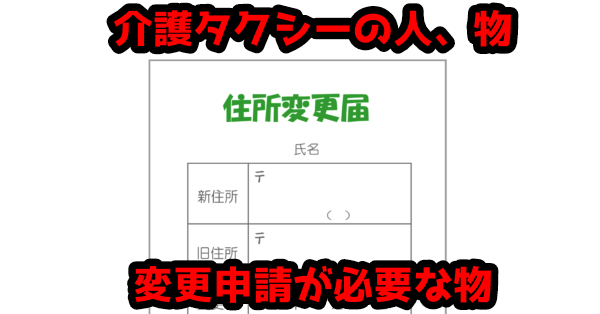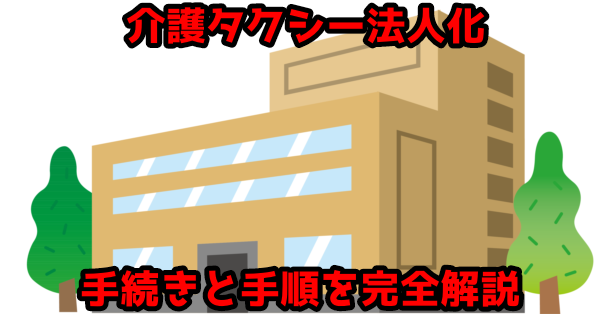救急車が逼迫していて、民間救急業者がコロナ禍で活躍したという話は結構広まり始めています。
- 介護タクシーと民間救急ってどう違うの?ほとんど同じ?
- 民間救急ってどうやったら開業できるの?
- 信号とか無視出来る?スピード出せる?
最近では「救急タクシー」という呼ばれ方もしていますが、正直この言い方の方が制度的にしっくり来る気がします。
民間救急を開業するには、消防署で研修を受けて認定を貰う必要があります。
では、消防署から民間救急の認定を貰うにはどうしたらいいのでしょうか。認定を貰ったらどんなメリットがあるのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、消防署から民間救急事業者に指定されるにはどうしたらいいか、どんな条件を満たせばいいかがわかります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
LINEでのご相談は無料です
民間救急とは救急車の逼迫を助ける民間事業者
現在、救急車が逼迫しています。新型コロナの流行前からも都心部では顕著でしたが、新型コロナ流行後は更に逼迫しています。
そこで、特に緊急性を要さない患者の搬送については民間救急を利用して下さいという動きを行政は強めています。
正式名称は「患者等搬送事業」
民間救急、正式名称は「患者等搬送事業」です。(以下民間救急)
救急車は緊急です。緊急を伴わない救急については、民間救急の利用を行政も推奨しています。
緊急を伴わない救急とは下記の通りです
- 通院
- 退院
- 緊急搬送後の帰路
- 転院
- 他、緊急ではないが車いすやストレッチャーに乗ったまま病院へ行きたい時
救急車と民間救急の違い
| 民間救急 | 救急車 |
| 有料 | 無料 |
| 信号、法定速度厳守 | 緊急走行が可能 |
| 赤色灯無し | 赤色灯有り |
| 医療行為無し | 医療行為あり |
| 病院からの帰り、通院、転院も可能 | 病院へ行くのみ |
上記のような違いが出てきます。民間救急は民間ですので、料金は利用者の負担になり、健康保険も適用できません。
ですが、車椅子やストレッチャーを貸してくれ、乗ったまま移動できるという高性能な運送サービスになります。
民間救急は儲かる?│どんなビジネスか
結局のところ、民間救急は旅客運送(介護タクシー)の許可の上で認定される資格になります。
介護タクシーの許可は絶対に取ることになるので、介護タクシーの仕事もしつつ民間救急の業務を強化していくのが従来のやり方です。
なお、介護タクシーが儲かる儲からない、については下記の記事に詳細記しましたのでご参考下さい。
民間救急の料金体系
民間なので、運賃や救急料金、器材レンタル料等の料金はかかります。
- 時間制or距離制運賃
- 介助料金または救急料金
- ストレッチャー、車椅子等の機材レンタル
- フロア移動、階段昇降料金
運賃部分については、タクシーと同様の運賃がかかり、救急料金も必ずかかります。
ストレッチャーも借りない人はおそらくいません。
これら合わせると、一回の搬送に1万~2万程度は売上があると見ていいでしょう。介護タクシーの料金体系とほぼほぼ同じです。
介護タクシー・民間救急の併業で年間売上は360~600万
民間救急を行うには介護タクシーの許可を取る事になります。
介護タクシーの年間売上が営業車1台辺り年間360~600万程度になります。
介護タクシーは朝昼の病院送迎以外で乗客を増やすのがなかなか難しいのですが、民間救急だと夜の乗客もプラスアルファ出来る可能性が上がります。
つまり1台辺りマックス600万以上が見えてきます。
民間救急を開業するための初期費用
まず、介護タクシーを開業するために300~400万程度必要です。
加えて民間救急の認定を受けるための追加資機材は、大まかに10万程度あれば揃います。(詳細下記の表にて)
既に介護タクシーを開業している状態で、民間救急を検討する場合は初期費用は誤差の範囲です。
民間救急の依頼は安定しない
救急なので、その性質上毎日決まった時間にあるようなものではありません。
介護タクシーは客数が増えれば安定しますが、民間救急の依頼は一発ものです。
消防署や保健所からバンバン紹介がくるわけでもありません。
つまり、病院や乗客に向けて「民間救急」という名前をアピールポイントとして、上手く売っていく必要があります。
原則、医療行為はしなくて良い
民間救急の車両には殆どの場合に医師や看護師や救急救命士が乗っていません。医師や看護師でない人は医療行為をしてはいけません。
消防署で民間救急の研修を受けてはいますが、医療行為が許可された人ではありません。
大前提として、あくまで旅客運送業という事になります。
民間救急事業者になるには│介護タクシーの許可と消防署の認定
民間救急事業者になるには、介護タクシーの許可を貰った後に、消防署や消防本部で、民間救急事業者の認定を貰う必要があります。
民間救急事業者の認定を貰うには、下記の4つの条件が必要になります。
- 介護タクシー等の営業許可を持っている
- 運転手と乗務員が、消防署などが行う患者等搬送乗務員基礎講習を受講している
- 福祉車両である(セダン型はNG)
- 車両に必要な備品を積んでいる
民間救急の事業者の認定を受けるには、介護タクシーの営業許可を持っていることが必要になります。
許可ではなく認定なので、必要な研修を終えた人材と設備を満たしていれば消防署が認定してくれます。
民間救急事業者認定までの流れ
上記の流れになります。
許可を得た後の許可になりますので、なかなか大変ですが、介護タクシー営業許可に比べれば講習と資機材の買い揃えと認定だけになりますので、かなり容易です。
民間救急の認定を受けるには福祉車両必須
介護タクシーはセダン型乗用車でも営業許可がおります。
ですが民間救急の認定を受けるには福祉車両でなくてはなりません。通常のセダン型では認定されません。
民間救急は下記の種類があります。
- 車いすストレッチャー両方乗車可能
- 車いすのみ乗車可能
どちらでも運営出来ます。
救急車と言えばストレッチャーというイメージがありますが、ストレッチャーを乗せられなくても、車いすのみでも民間救急業者の認定を受けることが出来ます。
ストレッチャーも載せられる車両の場合は乗務員が2名体制、車いすのみの場合は乗務員1名体制で行って下さい。
救急車と紛らわしい見た目はNG
あくまで民間で、緊急車両ではないので、下記の様な決まりがあります。
- サイレンはNG
- 赤色灯はNG
- 緊急車両ではないので交通ルールは守る
- 車のカラーが赤白なのはOK
つまり、まんま救急車の見た目はNGです。救急車と民間救急が見た目で区別できる必要があります。
赤色灯は駄目ですが、白に赤のラインが入ったハイエースは良いようです。
介護タクシーから民間救急認定の為の必要資器材
介護タクシーに加えて追加資機材を揃えるとすると、下記の機材が必要になります。認定の要件になります。
| 呼吸循環利用資器材 | ポケットマスク バッグマスク | ¥3,500 |
| 創傷保護用資器材 | 三角巾 包帯 ガーゼ 絆創膏 | ¥4,000 (ほぼほぼ消耗品) |
| 保温・搬送資器材 | タオル 担架 まくら 敷物 保温用毛布 | ¥46,000 |
| 消毒用資器材 | 噴霧消毒剤 各種消毒薬 | ¥5,000 |
| その他資器材 | はさみ ピンセット 手袋 マスク 膿盆汚物入れ | ¥16,500 |
| 合計 | ¥75,000 |
すごく大雑把に揃えるための概算してみました。10万かからないレベルで揃えることが可能です。
民間救急に酸素ボンベは必須ではない
あくまで民間ですので、本物の救急車のように酸素ボンベや医療器具を積んでおく必要はありません。
加えて注意したいのが、酸素ボンベは積んでおいても業者側で触ることは出来ないです。
酸素の吸入は医療行為に当たりますので、医師の指示を受けた看護師等の医療資格を持っている方以外は出来ません。
積んでおくことは出来ますが、看護師さんが居ない場合は患者さん自身でやって貰う必要があります。
24時間体制でなくてもいい
救急車と言えば24時間いつでも来てくれるというイメージですが、民間はあくまで民間ですので、24時間体制でなくても構いません。
9:00~18:00等の普通の時間帯で運営している所がむしろ多数になります。
殆どの場合、介護タクシーとの並行運営になるので、介護タクシーの営業時間だけ、民間救急も営業しています、と言う事でOKです。
夜間営業をしたくない場合は、営業時間外は断っても乗車拒否には当たりません。
民間救急事業認定の有効期限
民間救急事業者としては、認定されてから5年間有効です。5年後経ったら更新手続きが必要です。
ただ、民間救急事業者の認定のために必要な乗務員講習の有効期限が2年です。2年経ったら定期講習を受けないと無資格営業になります、忘れず受けて下さい。
民間救急の認定申請についてのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
LINEでのご相談は無料です
介護タクシーと民間救急並業のメリット
消防署や救急救命センターと連携できる
民間救急事業者のメリットとして、消防署と連携でき、消防署やそのコールセンターから患者さんを案内してくれることがあります。
民間救急の事業者として認定されると、消防局のホームページなどで事業者名が登録され公開されます。
加えて、消防署や消防署と連携するコールセンターが「緊急じゃないから救急車ではない」と判断した場合、民間救急業者を案内することがあるので、認定されて名簿に載っていると案内してくれます。
119もそうですが、救急車を頼むかどうか相談する窓口である「#7119」でも、救急車じゃないなと言うことになると、民間救急を案内することもあるそうです。
「民間救急」「◯◯消防局認定」等の名称独占
名称の独占が可能です。当然ながら認定を受けていない業者が「認定」等と言うと詐欺にあたります。
民間救急の認定を得たからと言って、介護タクシーだけの時と出来ることは正直変わりません。
ただ、民間救急という肩書をフルに活かして
- 病院
- 保健所
- 介護施設
- 救急救命センター
この辺りと連携を取ることが出来ればプラスアルファの売上を作ることが可能になってきます。乗客の間口はかなり広がるはず。
まだ自治体や行政側も活かしきれいていない制度なので、民間側から新しい提案をするタイミングとしては、今がベストなのかもしれません。
民間救急を並業した時のデメリット
介護タクシーに民間救急を加えた所で、特に介護タクシー業に何か制限が加わるような事はありません。
考えられるデメリットは下記の通りです。
- 10万弱の初期投資が必要
- 介護タクシーと民間救急の出動で車に積む機材が違う
- ストレッチャー対応だと乗務員が2名必要
まだ発展途上の制度ですので、このデメリットをメリットが上回るか下回るかの判断は、おそらく事業者様によって違ってくるのではと思われます。
今のところ、活かすも殺すも事業者次第というまだまだ新しい制度です。
弊所が調査した実際の消防署との連携状況
2022年中で、実際に消防署と連携して民間救急が発動した例は大阪全体で100件前後だそうです。そのうち
- 消防署の直接紹介:0件
- 救急安心センター#7119からの紹介:約100件
という実績でした。
ちなみに、これを教えてくれたのは寝屋川枚方消防組合の方ですが、寝屋川枚方での2022年の消防組合での民間救急の活用実績は10件とのことです。
年間なので、月一回あるかないかです。聞いた話ですと
- 「救急である、救急でない」の判断基準が難しく、基本救急車が出動している
- 行政の方でもまだ使いこなせていないというのが正直な所
という事だそうです。仮に「救急ではない」と案内をしてなにかあった時に責任問題になるので慎重な判断が必要ですが、そのノウハウや蓄積がまだないという事です。
まだまだ発展途上の制度です。尚、「#7119」救急救命センターについて、詳細は下記の記事もご参考下さい
コロナ禍では大活躍
消防署からの要請はまだあまりありませんが、コロナ禍では大活躍しました。
ちなみに今回の新型コロナの場合は消防署ではなく、保健所からの紹介だったそうです。
民間救急事業者は、消防署に名簿が乗り、業者名が公開されます。
その名簿が保健所に回り、保健所がコロナ患者に民間救急の紹介を行っているということです。
今後類似の自体が起こった場合には、再び活躍の場が来る可能性があります。
民間救急の指定を取りたいと思ったら
現在介護タクシー事業を行っていて
- 民間救急の指定も受けたい
- ストレッチャーを乗せられる車がないけど大丈夫?
- 救急の設備ってどんなものが必要?いくらかかる?
- 今ある営業車や設備でプランを立てたい
等疑問や希望があれば是非ご相談下さい。大枠の決まりから、具体的な設備を見てのご相談、承ります。下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
LINEでのご相談は無料です
まとめ
- 民間救急は介護タクシーの許可を持っていると認定を受けられる
- 介護タクシーとほぼ同じサービス形態
- 消防署やそのコールセンターから患者さんの紹介が受けられる
- 研修を定期的に受ける。研修にも認定にも有効期限がある
- 介護タクシーと相乗効果は高い
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。
LINEでのご相談は無料です
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。
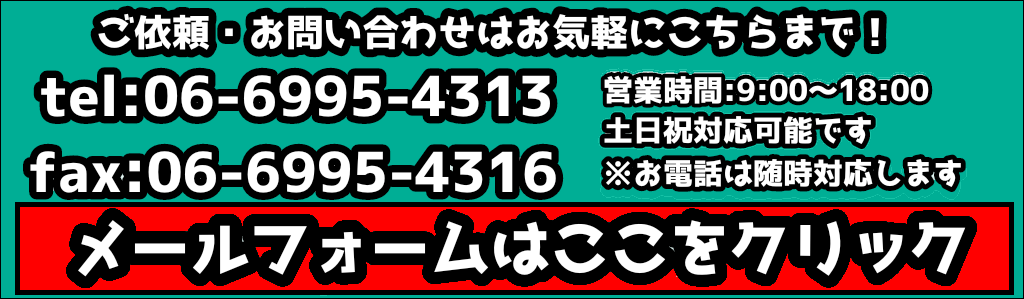
メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)