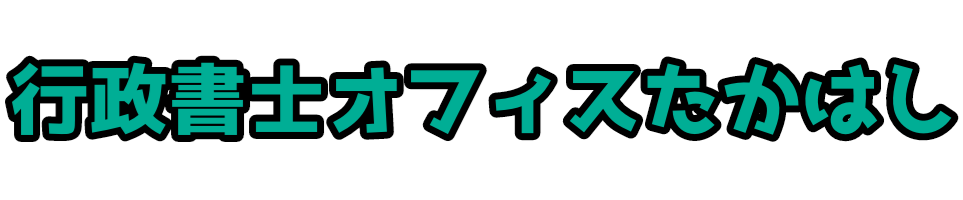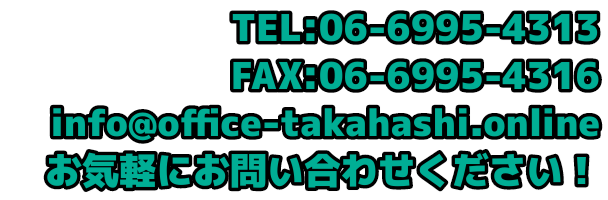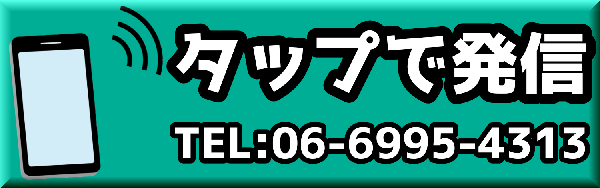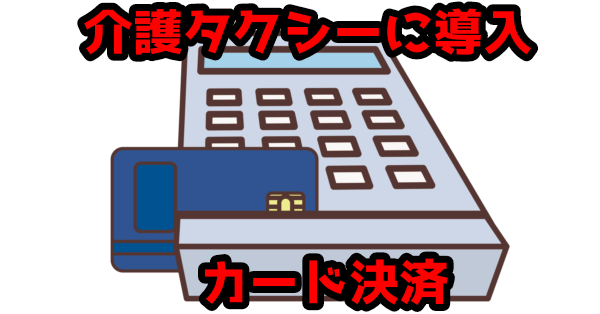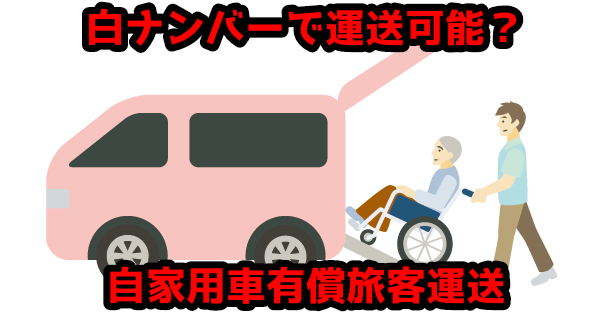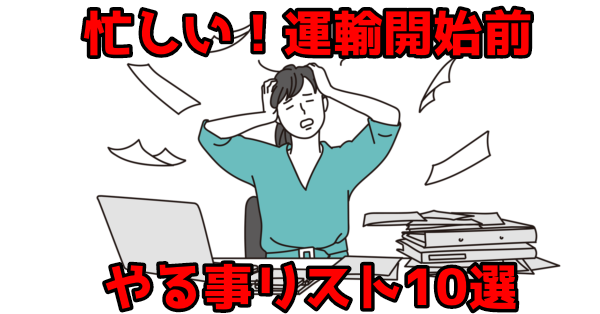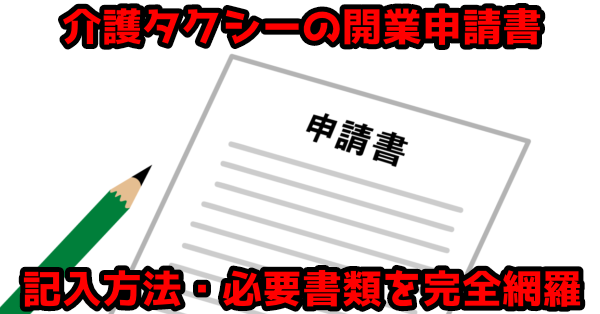
介護タクシー(福祉タクシー)を開業しようと準備を進め、人員、物件設備、資金が集まり、さあ開業しようとした時、許可をどうすればいいか知っていますか?
役所に営業の許可を取るようなことは、一生に1回あるかないかですので、知っている人は少ないと思います
- まず許可が必要なの?
- 許可は誰からもらうの?何処に取りに行くの?
- どういう風に申請すればいいの?何を出すの?
- 必要な書類は?
実はこれは全て法律や省令、運輸局の通達などで決まっています。許可を取らないで始めると無許可営業になります。
まず準備物が必要です。準備物がすべて揃ったら書類を集め、作ることが出来ます。
上記記事にある人員、物件、資金を集めきったのであれば、申請書のマスを埋めるのは簡単です。
この記事を最後まで読むと、介護タクシー(福祉タクシー)の開業準備を終えた後に、許可申請の書類の書き方や、添付する証拠書類等何を揃えればいいかがわかります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
介護タクシーの申請書を代わりに作ってほしい場合「初回無料相談希望」と下記LINE、お電話でご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。申請を代行してほしいという場合は下記のリンク先御覧ください。
介護タクシー開業のための準備物を揃えて申請書に落とし込む
準備が終わったらそれを全て申請書に書き込んでいく必要があります。
準備さえ終わっていれば、申請書は全て埋まります。申請書を書く段階で書き込めないところがある場合、そこが準備不足の点です。
- 人員
- 施設設備
- 資金
図面や詳細仕様等を書き込んで、証拠書類等も収集して添付すると、約1cm程度の暑さの申請書の束が出来上がります。
そんな厚さ1cmもある書類の束を作れる気がしないという場合は申請書作成代行を弊所で行っています、まずは下記の「初回無料相談」をご利用下さい。
東海地方(愛知・岐阜・三重・静岡・福井)での申請詳細はコチラ
北陸信越地方(石川・富山・新潟・長野)での申請詳細はコチラ
介護タクシーの営業許可申請を代わりにしてほしい場合「初回無料相談希望」と下記LINE、お電話でご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
介護タクシー許可申請1「書面を入手・ダウンロードする」
大阪での許可の申請は「近畿運輸局」に対して行います。提出については各府県の運輸支局に提出します。
それ以外の地域も各運輸局の本局に対して申請、窓口は都道府県の運輸支局になります。
介護タクシーは運送業ですので、運輸局です。
介護タクシーの開業許可申請の書面は近畿運輸局のホームページからダウンロードできます。
それ以外の地域も、各地運輸局本局のページに申請書があります。ダウンロードして書き込んでいってください。
印刷して手で書き込んでもいいですし、エクセルファイルですので、ファイルに書き込んでから印刷するも良しです。
詳しい方法は、下記の記事までご参照下さい。
近畿地方以外の運輸局については、下記の記事もご参考下さい。
東海地方(愛知・岐阜・三重・静岡・福井)での申請詳細はコチラ
北陸信越地方(石川・富山・新潟・長野)での申請詳細はコチラ
介護タクシー許可申請2「事業計画書」を書く
施設の詳細や自動車の詳細、台数などを書き込みます。
- 営業所、休憩所、車庫の住所
- 各施設の大きさ、面積
- 賃貸か自己所有か
- 賃貸期間
契約書や見積書通りに書き込むだけなので、難しく考えることはないでしょう。
具体的な記入例は、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー許可申請3「運行管理体制」を書く
人事についての組織図を書き込みます。役割分担はこの時点で大体決まっていると思います。
1人開業が可能な地域はすべて同じ人の名前を書いてOKです。
2人開業の地域は、運転者と運行管理者・指導主任者を同じ人にしないようにだけ注意して下さい。
具体的な記入例については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「運行管理体制」決め方・書き方はコチラ!
各地域の運輸局の違いについては下記の記事もご参考下さい。
東海地方(愛知・岐阜・三重・静岡・福井)での申請詳細はコチラ
北陸信越地方(石川・富山・新潟・長野)での申請詳細はコチラ
介護タクシー許可申請4「資金計画」を書く
車両、土地、建物、人件費、その他経費、保険税金等開業後1年間でどれくらい必要になるかを計画します。
この表により
- 開業直後2ヶ月に必要な経費全額
- 開業後1年に必要な経費の半分
が、いくらになるかわかり、その両方を上回っている資金があれば資金要件はクリアー出来ます。
尚、具体的な記入方法は下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「資金計画」計算方法・書き方はコチラ!
介護タクシー許可申請5「資金調達方法」を書く
資金の調達方法を提出します。
- 個人の場合は銀行残高の大体の額
- 法人の場合は前期の貸借対照表の流動資産状況
上記が必要です。ここで書くのはあくまで参考値です。最終的には残高証明で残高を見られます。
尚、具体的な記入方法については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー許可申請6「建物関係の宣誓書」に記名する
書類の概要としては、営業所、休憩所、車庫(建築物の場合)について下記4法に違反しないという宣誓です。
これらに違反している建物だと発覚した場合は許可を取り消しても文句を言わない、という宣誓書です。
加えて用途地域の確認や、自治体への営業所の設置の可否の確認を口頭でもらって書面に記入する所もあります。
尚、各書面の詳しい解説については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「建物関係の法令に違反しない宣誓書」書き方はコチラ!
介護タクシー許可申請7「欠格事由に該当しない宣誓書」に記名する
介護タクシーを開業出来ない人リストが法律に羅列されており、そのリストに私は該当していませんという宣誓をします。
主な所として下記の4点です。
- 5年以内に禁錮以上の刑を受けた
- かつて運送業を経営していて処分を受けた
- 処分を受けた運送業の役員をやっていた
- 5年以内に白タクや白トラで捕まった
宣誓書の書き方については下記の記事を御覧ください。
介護タクシー営業許可申請書「欠格事由や法令遵守の宣誓書」書き方はコチラ!
詳しい欠格事由がどんな物かについては、下記の記事の該当項目を御覧ください。
介護タクシー許可申請8「就任承諾証」に就任予定の人を書く
開業許可を受けたら、この人がこの役割に就く事を承諾しますという旨の書面を書きます。
上記の4人事につき1枚ずつ、合計4枚書きます。
1名開業地域だと、全て同じ人の名前でOKです。
2名開業地域だと、運行管理者と運転者に同じ人の名前が書いていると許可が下りませんので、気をつけて下さい。
尚、各書面の詳細な解説については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「各役職への就任承諾書」書き方はコチラ!
各地域別の申請については下記の記事も御覧ください。
東海地方(愛知・岐阜・三重・静岡・福井)での申請詳細はコチラ
北陸信越地方(石川・富山・新潟・長野)での申請詳細はコチラ
介護タクシー許可申請9「法令試験申込書」を書く
許可を申請すると、法令試験を受けなければなりません。
法令試験後に審査が始まる場合と、書類審査終了後に法令試験を受験するパターンがあります。各地域の運輸局により変わります。
申請書に法令試験申込書が付いているので、申請と同時に試験を申し込みます。
試験は1ヶ月に一度なので、落ちると審査、そして許可が1ヶ月伸びます。
すでに物件を借りていて、空家賃が発生している場合は経済的にも損失になるので、必ず一発で受かりたいです。
尚、法令試験の具体的な内容については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー営業許可申請書「法令試験申込書」書き方はコチラ!
尚、法令試験は各地運輸局本局で行われます。大阪や新潟、名古屋や広島まで行かなければなりませんので予定をしておいてください。
介護タクシー許可申請10「運賃認可申請書」で運賃を設定
運賃の認可を受けないとタクシーメーターの設定が出来ません。認可申請書を提出します。
近畿管轄内の場合は営業許可申請書と同時に運賃認可も出すことが出来ます。北陸や中部など近畿以外の地域は許可後に運賃認可申請を提出して認可を受けます。1ヶ月程度で認可が下ります。
運賃は自由に決められるわけではなく、タクシーと同じ認可運賃制で、各営業区域で決められた数パターンの中から選ぶことになります。
自動認可運賃を選ぶと、一回一回審査がなく、年一回の審査もありません。
認可運賃と共に割引適用や迎車料金の有無も決めます、一度決めると1ヶ月は変えられない上にタクシーメーターの設定変えは有料ですので慎重に選んで下さい。
詳しくは下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー許可申請11「必要添付書類」のリスト
申請書を書くと、その申請書に書いたことが真実であるかを証明するために証拠書類を添付することになります。
主に必要な物は下記リストです。
- 施設や車庫の平面図
- 施設や車庫(予定地)の写真
- 土地建物の登記簿(自己所有の場合)
- 賃貸借契約書、使用承諾書(賃貸の場合)
- 幅員証明書
- 前面道路の宣誓書(幅員証明書廃止の自治体のみ)
- 営業車の見積書(購入、リース)
- タクシーメーターの見積書
- 任意保険の見積書
加えて法人の場合追加で
- 定款のコピー(原本証明の判子つき)
- 登記事項証明書
これらが必要になります。
役所から取り寄せる物、業者からもらうもの、自分で作る物等様々です。
添付書類の詳細については、下記の3記事をご参照下さい。
介護タクシー開業申請添付書類、自分で作る物
介護タクシー開業申請添付書類、役所で集める物
介護タクシー開業申請添付書類、業者から貰う物
効率よく手に入れ、スムーズに申請したいです。
介護タクシーの許可のための書類集めを代わりにやってほしい場合「初回無料相談希望」と下記LINE、お電話でご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。
申請から許可まで2ヶ月の待ち時間
申請から許可まで、審査期間があります。支局の窓口で簡易に書類の不足などを見てくれ、内容に審査については各地運輸局の本局で行います。補正の指示等も本局から連絡が来ます。
申請から許可まで大まかに2ヶ月かかります。この期間についてはどれだけスムーズに行っても役所内部の事(標準処理期間)になりますので、短縮が出来ません。
近畿管轄内の場合は各月末日の場合が多いです、それ以外の地域も大体2ヶ月かかります。2ヶ月超えて連絡がなければ一度連絡してみましょう。
リースや賃貸の場合は、大家さんが許してくれるのであれば開始時期を「許可後」という条件にするなどして、空家賃を減らし、リースの開始は許可が下りてからにする等して工夫しましょう。
申請書は、内容を運輸局に電話で確認したり、間違っていたら書類が返ってきて、書き直してまた提出したり、なかなか困難です。
書類の作成や役所とのやり取りが苦手な事業者様は代行をご利用下さい
役所へ書類を出し、審査が始まると役所から電話が掛かってきて、書面の内容について質問等されます。すぐ答えられればいいですが、調べて折り返し回答等の事も少なくないです。
枠一つ記入が間違えていれば補正依頼が来ます。役所で勝手に書き換えてくれる事はありません。この往復時間分だけ、許可が先に伸びてしまいます。
これらのやり取りを苦手、面倒だと思う場合、弊所にお任せ下さい。
行政書士に代行を依頼すると、こういった連絡は全て行政書士に直接されることになります。運輸局との書面のやり取り、電話対応、調べてからの回答等は可能な限り弊所で請け負います。
介護タクシーの1台当たりの平均売上は50万とも言われていますので、1ヶ月早く開業できれば、将来の50万の売上がその分早く確保できます。
お気軽に下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEでのご相談は無料です
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。
LINEでのご相談は無料です
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。
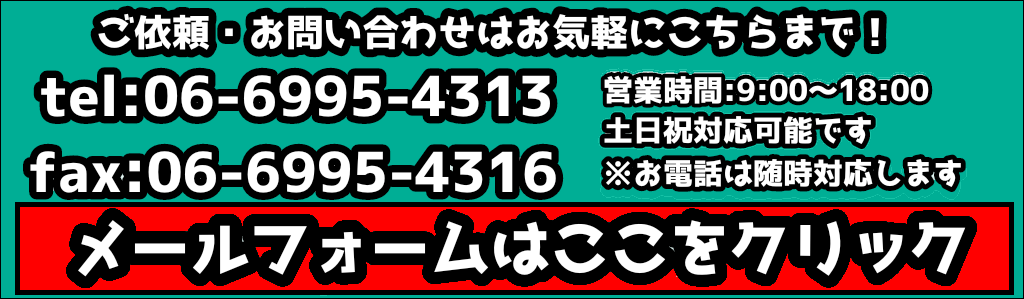
メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)