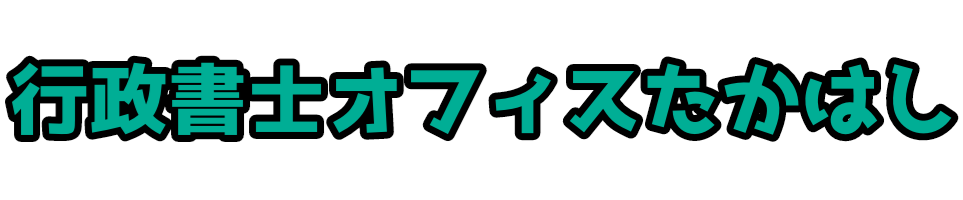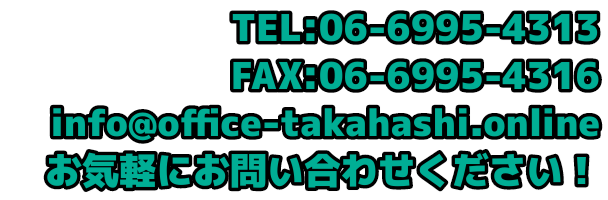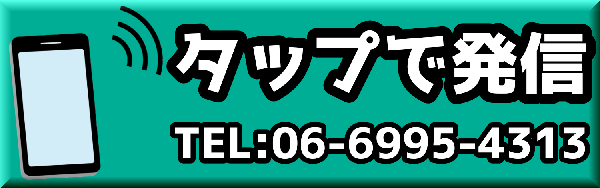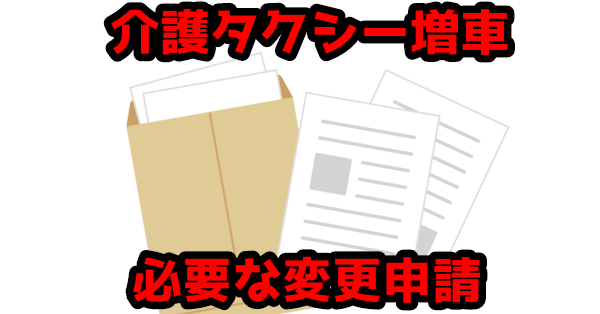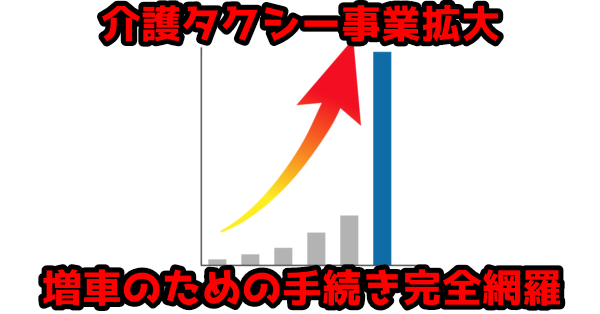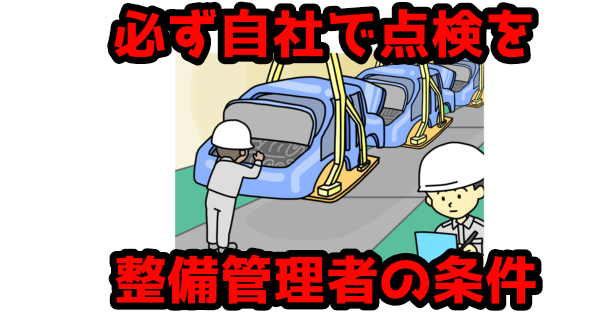
介護タクシー(福祉タクシー)の開業許可申請をするにあたって、人事を決めなければなりません。
その一つが整備管理者です、運転者や他のポジションと兼任が出来ますが「名前書いても整備なんて出来ないけどいいの?」なんて思うこともあるでしょう。
因みに主要人事とは
の4つです。実は介護タクシーは5台未満である場合は、整備が出来なくてもなることが出来ます。
大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、開業申請書類の整備管理者の欄に誰の名前を書けば一番良いかがわかります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
介護タクシーの役割分担をどうしたら良いか等のご相談は、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
介護タクシーの許可には最低人数と役割分担が必要
最低人数は1名か2名です。地域によって変わります。
1名なら全ての役割を一人の方が出来ます。
2名の地域の場合は役割分担が必要です。「運転手」「運行管理者」「指導主任者」について兼任不可になっている地域です。
介護タクシーの人事について詳しくは下記の記事をご覧下さい。
人事以外の介護タクシーの開業のための全条件については下記の記事もご参照下さい。開業には「ヒト・モノ・カネ」が必要です。
介護タクシーの整備管理者は誰でもなれる
介護タクシーを5台未満で開業する場合は、整備管理者に整備士や実務経験などの資格は必要ありません。
誰でもなれますが、空席はNGなので新規開業の時には必ず選任されている必要があります。
資格がない人でもなれますので、実際の整備業務は自動車整備工場に振れますが、点検の方向性と点検業務については責任を持ってやらなければなりません。
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車につき、点検整備、整備管理者の選任及び検査に関する道路運送車両法の規定に従う他、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
道路運送車両法 第四七条の2より抜粋
一、事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離等の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。
前号の点検及び整備をした時は、道路運送車両法第四九条(点検整備記録簿)の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
介護タクシーの整備管理者の役割
整備管理者は、営業車の整備管理をする役割です。営業車が5台未満の場合は日常点検と、定期点検や車検に出すスケジュールを管理する事が主な役割になります。
- 車の日常点検の方法を決める、日常点検する
- 点検の結果、車の使用の善し悪しを判断する。
- 日々の点検の記録をする。
- 定期点検の方法を決めて実行する。または外部の整備工場に頼む
- 点検の結果、必要な整備を整備屋さんに頼む。
点検の記録はしっかり取って保存するようにして下さい。事故等あった時に該当の営業車の点検記録等の提出を求められる事があります。
∙ 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること
国交省通達 国自整59号より抜粋
∙ 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
∙ 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
∙ 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
∙ 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
∙ 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
∙ 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
∙ 自動車車庫を管理すること
∙ 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること
日常点検の項目
運送業の事業用自動車の日常点検は1日一回以上が義務付けられています。記録も必要なので安全のためにも必ずやるようにして下さい。
下記は国交省で推奨されているチェック項目です。チェックシートを作ってチェックしていくのがお勧めです。
- タイヤの空気圧
- タイヤの亀裂・損傷・異常摩耗・スリップサイン
- 冷却水量
- ブレーキ液量
- ランプ類の点灯
- エンジンオイル量
- バッテリ液量
- エアタンクの凝水
- パーキングブレーキの引きしろ
- ウォッシャ液
- ワイパーの拭き取り状態
- エンジンのかかり具合・異音
- エンジンの低速・加速
- ブレーキの踏みしろ、効き具合、異音
定期点検を忘れないように
事業用自動車については、3ヶ月に1度の定期点検が義務付けられています。
介護タクシーの場合は整備士保持の整備管理者が居ることが少ないので、整備工場に三ヶ月に一度点検に出します。
上記国交省通達の通り、定期点検については外部の整備工場にやってもらってOKですので、整備管理者に選任されている人は忘れずにスケジュールしましょう。
介護タクシーの整備管理者に必要な資格
営業車が5台未満の場合
営業車が5代未満なら資格はいりません。
整備管理者はどのポジションとも兼任ができますので、選任して申請しましょう。
営業車が5台以上の場合
- 1~3級自動車整備士
- 2年以上の実務経験の後に研修を受けた人(整備管理者選任前研修)
整備士資格持ちにしても、実務経験要件にしても、実務経験が必要です。なぜなら整備士の受験資格にも1年の実務経験が必要だからです。
この為に整備工場で1年や2年働くのは現実的ではないので、5台に増やす前に整備士を雇用することを検討して下さい。
実務経験で整備管理者になる方法
整備士資格を持っていなくても、実務経験があれば整備管理者になれます。
- 整備工場、特定給油所で整備要員として2年以上働いていた
- 運送業で実際に整備管理者の整備要員として2年以上働いていた
これを満たしている人が「整備管理者選任前研修」を受けると整備管理者になれます。
実務経験の証明については、前に働いていた整備工場や給油所から「実務経験証明書」出してもらう必要があります。何年何月~どの業務に就いていた等の表と共に、会社の判子が必要です。
ただし、介護タクシーの整備管理者に選任されていても、実際の整備業務は外部の工場に出していたという例だと、整備の実務経験としては認められない可能性が大です。
整備士資格で整備管理者になる方法
4輪用の3級以上の整備士資格があれば、研修を受ける必要もなく整備管理者になれます。
実は整備士資格にもかなりの種類があります。
◯一級小型自動車整備士
◯二級ガソリン自動車整備士
◯二級ジーゼル自動車整備士
◯二級自動車シャシ整備士
✕二級二輪自動車整備士
◯三級自動車シャシ整備士
◯三級自動車ガソリン・エンジン整備士
◯三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
✕三級二輪自動車整備士
「一級大型自動車整備士」と「一級二輪自動車整備士」もありますが、現在、これらの資格の試験が行われておりません。
介護タクシーの整備管理者になるには、◯を持っていればいいです。2輪の整備士は資格を満たしません。
整備管理者については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
整備管理者の外部委託は出来ない
整備管理者に外部の整備工場を設定する事は原則できません。
- 整備管理者に外部の業者を指定できない
- 自社のグループ(子会社・親会社など)に整備工場があれば委託出来る
- 点検は必ず自社、点検の上での整備実作業は外部の整備工場に依頼できる
点検まで整備屋さんに丸投げしたり、外部の整備屋さんを整備管理者に選任したりはできないので注意してください。
グループ会社に整備工場があるというパターンは、大きいタクシー会社でも無い限りあまりない例ですが、逆に自動車整備工場が介護タクシー事業に乗り出している例は見られます。
点検メニュー(上記参考)を作って、点検をする所までは必ず自社の整備管理者がやりましょう。
車の台数に応じた必要人数
営業所ごとに1台以上で必ず1人以上必要です。
車の大きさ、台数によっても必要人数が変わってきます。
介護タクシーを想定すると、最大でもハイエースの10人乗りになりますので、11人乗り以上の車がある事はありません。なので
- 5台以上は資格持ち一人
- 5台以下は資格なし一人
と覚えておいて下さい。
道路運送車両法第五十条
道路運送車両法施行規則第31条の3 整備管理者の選任より抜粋
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
↓
道路運送車両法施行規則第三十一条の3
法第50条第1項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。
(中略)
三、乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車および乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 5両
(中略)
必要な研修
整備管理者選任前研修
整備の実務経験がある人が、整備管理者になるために選任前に受ける研修です。
整備士資格を持っている方が整備管理者になる時は、受講は免除されます。
整備管理者選任後研修
整備管理者の方が、年一回程度定期的に受ける研修です。
全員受講する義務があります。忘れずに受けるようにしましょう。
旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路輸送法第五〇条の規定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けた時は、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。
旅客自動車運送事業運輸規則第四十六条 整備管理者の研修から抜粋
一、整備管理者として新たに選任した者
二、最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過したもの。
整備管理者と他ポジションとの兼任
整備管理者はどのポジションとでも兼任が可能です。
- 指導主任者と兼任が出来ます。
- 運行管理者と兼任が出来ます。
- 運転者と兼任が出来ます。
運行管理者と兼任、運転者と兼任の両方のパターンがあります。
人事変更の時の届出
整備管理者の方の変更には運輸局に選任届が必要です。忘れずに提出しましょう。
選任届には、実務経験証明書や資格証の写し、研修の修了証等を添付する必要があります。
営業車が5台未満の場合は特に何も必要ありません。
整備管理者については、空席状態が許されませんので、必ず誰かを選任しておくようにしましょう。
整備管理者を誰にすれば良いか迷ったら
例えばこんな事で迷った場合
- 整備管理者を誰にしたらいいのか
- 整備ができるような人は居ないけどどうしたらいいのか
- 整備士を雇えばいいのか、いきなり人を雇う余裕はない
どういった人が整備管理者になれるのか、どういった人をあてればいいのか、介護タクシー専門の行政書士が直接ご相談させて頂きます。
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
まとめ
- 整備管理者はかならず一人以上必要
- 5台以下なら誰でも1人
- 5台以上だと整備士資格持ち1人
- 点検方法を決めて、そのとおりに点検、整備が必要なら整備する、または整備屋さんに依頼する。
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。
LINEでのご相談は無料です
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。
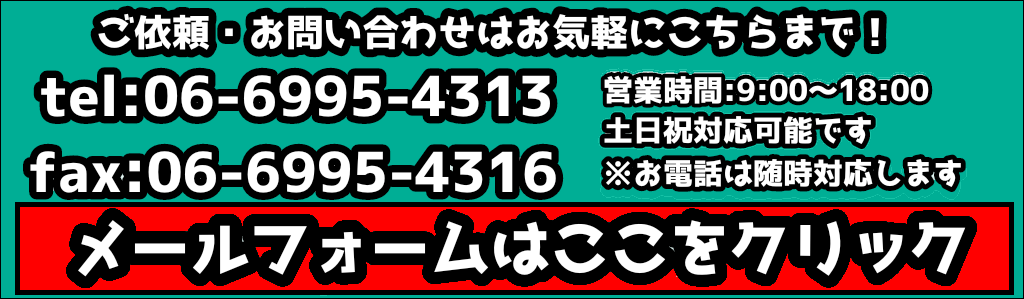
メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)