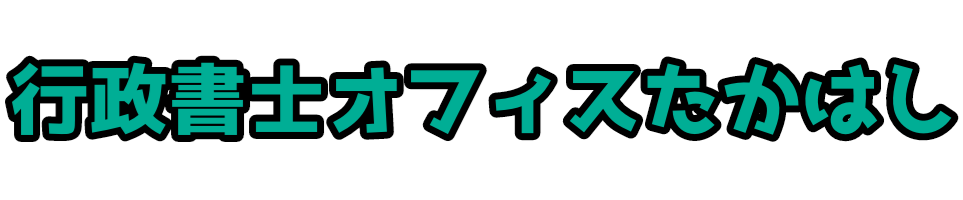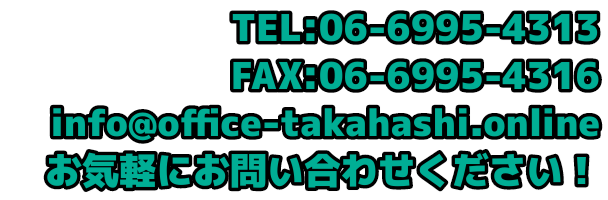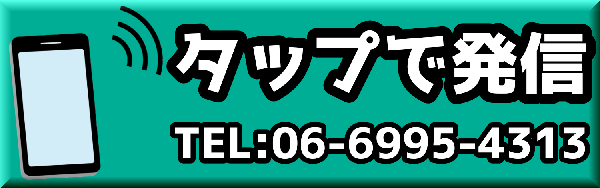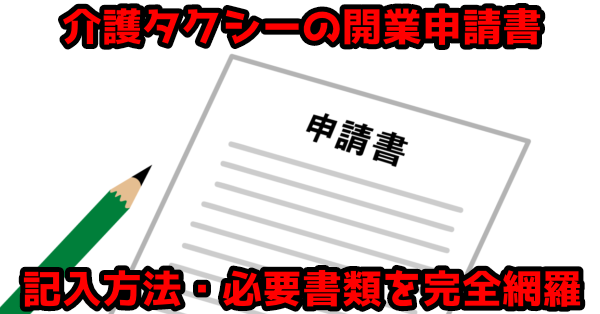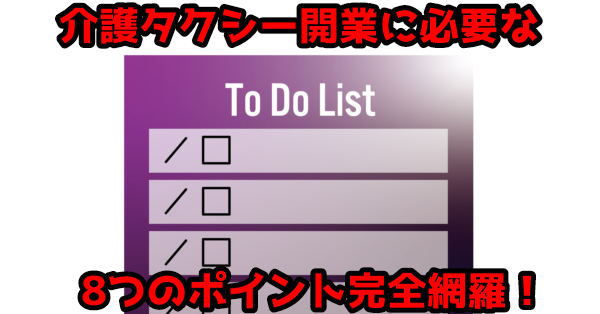介護タクシー(福祉タクシー)を開業するにあたって、何か資格が必要なのかと調べたことはありませんか?
- ニ種免許は必要なの?
- 介護系の資格も必須なの?
開業許可申請を書き込むにあたって必ずといっていいほど気になる事です。
実は介護タクシーの運転手になるのに、介護系の資格は必ず必要というわけではありません。
介護系の資格が必要ない時というのは、どういう時なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、運転者がどんな資格を持っていればいいのか、どんな人が適格かがわかります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
介護タクシーとタクシーのドライバーの役割の違い
介護タクシーは予約のみで依頼を受けます。
一般のタクシーは「流し」と言って、街を走り手を上げた人を拾うことが出来ます。介護タクシーはこれが出来ません。禁じられています。
予約のみとなり、その90%が病院への送迎となるので、病院開院時間以外は予約がほぼほぼ来ません。
流しを行うことで労働時間が伸び、効率が落ちますが、予約のみになる事でオンオフがはっきり出来ます。
勿論、事業主であればこれ以外の時間に予約電話があれば、それを受けることも出来ます。
介護タクシーの運転者の必要資格
福祉自動車で営業する場合
第二種自動車運転免許のみでOKです。
福祉自動車とは、車いすやストレッチャーを乗車させる設備がある車です。介護タクシーとして大半の人はこっちを思い浮かべるのではないでしょうか。
勿論介護系の資格があるに越したことはないのですが、必須ではないので許可はおります。
許可待ち時間が2ヶ月あるので、その間に取得するという事も可能です。
福祉自動車の運転者の努力目標
福祉自動車(乗降設備付き)を運転する運転者には努力目標が課されています。
- ケア輸送サービス従事者研修の修了
- 福祉タクシー乗務員研修の修了
- 介護福祉士の資格の取得
- 訪問介護員の資格の取得
- サービス介助士の資格の取得
上記の資格を取ることに務めなければなりません。
2,福祉輸送自動車に乗務する運転者等
国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋
(1)福祉輸送自動車のうち、福祉自動車に乗務する者は以下の①~⑤のいずれかの条件を満たすよう務めなければならない。
① 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施⑧するケア輸送サービス従事者研修を修了していること(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という)
②財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を終了していること。
③介護福祉士の資格を有していること
④訪問介護員の資格を有していること
⑤サービス介助士の資格を有していること。
この中で一番お手軽に取得できるのが「サービス介助士」です。
費用は5万以内、通信が基本で3~4日実技やオンラインでの講習もあり、検定に合格すると資格がもらえます。
①と②は法律には書いてあるものの、廃止されていて現在では受けられません。
セダン型等の自動車で営業する場合
セダン型(等)ですので、福祉自動車以外の乗用車を指します。資格は下記の物が必要です。
第二種自動車運転免許に加えて下記の資格のどれか一つが必要です。
福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する者は、以下の①~④のいずれかの要件を満たさなければならない。
国自旅第169号より抜粋
① ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
② 介護福祉士の資格を有していること。
③ 訪問介護員の資格を有していること。
④ 居宅介護従業者の資格を有していること国土交通省通達
福祉自動車のような車いすやストレッチャーを乗せやすい自動車に比べて、セダン型等(いわゆる普通の乗用車)は乗客を乗車させる難易度が上がるので、福祉系の資格が必須資格になります。
介護タクシーに必要な資格と予算
第二種自動車運転免許
人を載せてお金をもらう運送業になりますので、どんな状況でも絶対に必須です。
二種免許に必要な時間と予算は下記のとおりです。
| 受験資格 | 21歳以上 運転歴3年以上(停止期間除く) |
| 予算 | 20万前後 |
| 所要時間 | 合宿で8日、通学で20日前後 |
| 試験頻度 | 随時 |
介護職員初任者研修
福祉自動車ではないセダン型で開業したい時は必須資格です。
ただ、福祉自動車で開業する人でも、介護業界初参入の場合はこの資格の取得により基礎を学ぼうとして取得して来る方が多い人気資格になります。
| 受験資格 | 特になし |
| 予算 | 5万~13万 (スクールによる) |
| 時間 | 130時間 (2~3ヶ月) |
| 試験頻度 | 資格予備校など、どこかしらでやっている |
介護の基礎知識を一通り学ぶことができ、予算もお手頃で名刺にも書けて資格知名度も高いので色々と有利になることが多いです。
尚、介護タクシーの開業に必要な資格については下記の記事もご参考下さい。
【開業前必見】介護タクシーに必要な資格リスト8選・取得方法・時間と予算
介護タクシーの運転者の役割
運転をして利用者を安全に目的地まで運ぶ
運転手ですので、基本は運転をすることにあります。
介護タクシーは運転以外にも付加価値を付けることができます。
乗降介助
タクシーの乗り降りを手伝います。
リフト式、スロープ式、回転椅子式等の車がありますが、これらに利用者を乗車させて固定を行います。
介護タクシーではない一般のタクシーでは乗降の手伝いは許されていませんが、介護タクシーはこれを報酬を頂いて行うことが出来ます。
院内介助
病院へ送迎した後、院内での介助も行う事が出来ます。
院内での移動の手伝い、診察への同席、医師の話の記録とご家族への報告、薬の受け取り代理等を報酬を頂いて行えます。
オプションになりますので、これは行っていない業者もあります。
フロア移動
エレベーターのない建物の階の昇降については、持ち上げて移動等する場合にフロア移動をすることがあります。
人員が二人以上、または階移動のための設備等が必要になりますので、このサービスを行っている事業者は少数と思われます。
待機
介護タクシーの利用は、9割が病院への送迎になりますので、病院へ送った後、終わるまでの待機を求められる事もあります。
待機料金を貰っても、メーターオンのまま停車時の加算を頂いても良いです。
ケアマネージャーへの報告
報酬をもらってする業務ではありませんが、ケアマネからの紹介で依頼が来た場合、病院などでの医師の話の記録を報告しておくと、リピートにつながる可能性が上がります。
ケアマネージャーは一人に付き35人~40人近くの要介護者を担当しているので、紹介の裾野が広くなります。
運転者の必要要件
運転者を専任する場合、下記の条件に当てはまっている人にしなければなりません。
第二種自動車運転免許が必要
お客様を乗せて料金を頂く場合は必要です。どんな状況でも、二種免許保持者は必ず一人以上必要になります。
日雇いの人はだめ
正規で雇われている人がドライバーになれます。
時給やパートでも構いませんが、給料日払いの不安定な雇用の場合は、業務に影響が出ますので禁止されています。
2ヶ月以内の雇用契約しか無い人はだめ
2ヶ月以上は雇わなくてはなりません。
雇用契約期間が日雇いや週払いの場合だと業務が不安定になるので禁止です。期間が設けられていても2ヶ月以上。長く働いてもらえる人が望ましいです。
試用期間中の人はだめ
試用期間が終わる前にドライバーにはできません。
試用期間に研修等行う場合は、研修が終わってから運転手にして下さい。試用期間は義務ではないので、いきなり正規雇用でも問題は有りません。
14日以内のスパンでお給料を貰う人はだめ
日給日払い週払い等の人は駄目です。
日払い週払いだと、給料が出た後すぐ辞められてしまうので業務が不安定になり、禁止です。月給制が望ましいです。
運行管理者ではない人
大阪で介護タクシーをする場合、点呼をする人とドライバーの兼任はできません。
大阪では運転手と運行管理者は唯一兼任ができない役割になります。自分で自分を点呼出来ないので、運行管理者でない人を運転手にして下さい。
つまるところ運転者は正規で雇われて、今後も長期に渡ってドライバーを続けて行ける人でないとなれないと決まっています。
運転者は「二種免許取得見込み」でも許可が下りる
運転者になる人は申請の時点では第二種自動車運転免許を持っている必要がありません。取得見込みで構いません。申請から2ヶ月以内に取得できる根拠があれば、申請の受理の妨げにはなりません。
もちろん営業開始までに取れていなくて、そのまま営業すると無許可営業になるので、絶対に予定通り取りましょう。
・旅客自動車運送事業運輸規則 第三十六条
国土交通省令より抜粋
旅客自動車運送事業者は、次の各号の一に該当する物を前条の運転者その他事業用自動車の運転者に選任してはならない。(個人タクシー専業者を除く、)
一、日日雇い入れられる者
二、二月以内の期間を定めて使用されるもの
三、試みの期間中の者(一四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
四、十四日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者
(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む)
運転者は必ず一人以上専任しておかないといけない
運転者については一番最初に誰が行うか決まっていると思いますので、開業許可の申請用紙にはその人の名前を書きましょう。
当たり前ですが、ドライバーが一人も居ない状況は許されません。欠員が出そうな場合、速やかに補充を行わなければなりません。
・旅客自動車運送事業運輸規則第三十五条 運転者の選任
国土交通省令より抜粋
旅客自動車運送事業者は、事業計画の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。
他ポジションとの兼任
✕運行管理責任者と兼任
○指導主任者と兼任
○整備責任者と兼任
ここまでが運転者の役割や概要です。介護タクシーと言うからには運転者の方が事業の顔となります。それにふさわしい方を選任して下さい。
尚、その他の人事の詳細は下記の記事をご参照ください。
運転者の必要資格について知りたい時
どういう形での事業にしたいかをご相談下さい。それによって
- 二種免許だけでOK
- 二種免許の他に介護系資格も必要
に分かれます。二種免許だけは絶対に必要です。
誰に二種免許を取ってもらうのか、はたまた自分で取るのか、今後の事業計画によって迷わず決めることが出来るはずです。
介護タクシー開業のための運転手以外の人員、資金、設備の条件はコチラ!
事業計画は、開業許可申請時に必ず立てることになるので、行政書士は得意としております。
まずはお気軽に下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEでのご相談は無料です
介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト
介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。
下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。
- 介護タクシー開業の最低人数・必要資格
- 介護タクシー開業に必要な4つの設備
- 介護タクシーの許可が取れる最低限の資金
- 介護タクシーの許可が取れる「営業所」
- 介護タクシーの許可が取れる「休憩所」
- 介護タクシーの許可が取れる「車庫」
- 介護タクシーの許可が取れる「営業車」
- 介護タクシーの許可が取れる「運転者」
- 介護タクシーの許可が取れる「運行管理者」
- 介護タクシーの許可が取れる「整備管理者」
- 介護タクシーの許可が取れる「指導主任者」
- 介護タクシーの許可が取れない「地域」
4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。
購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。
まとめ
- 運転者は二種免許があればヨシ!
- 日雇い等でなく、正規で長期雇われている人ならヨシ!
- セダン型等の場合、介護の資格4種どれかが必須。
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。
LINEでのご相談は無料です
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。
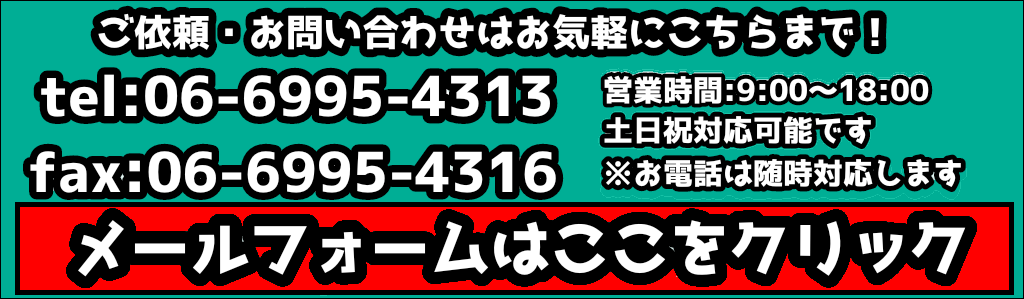
メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)