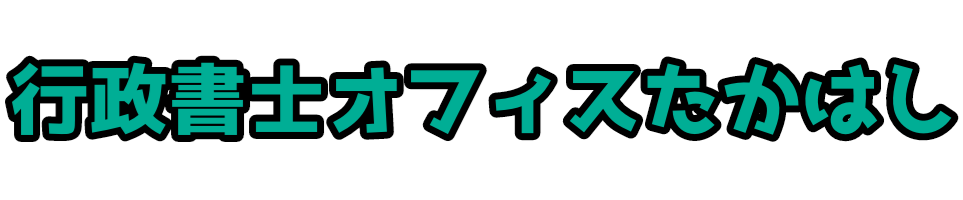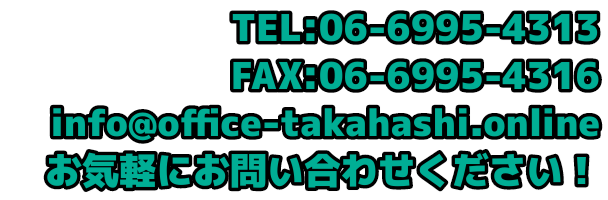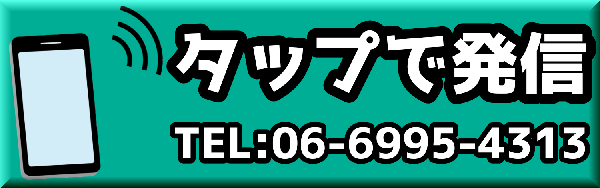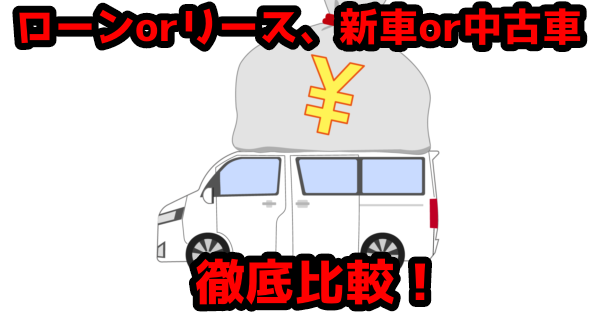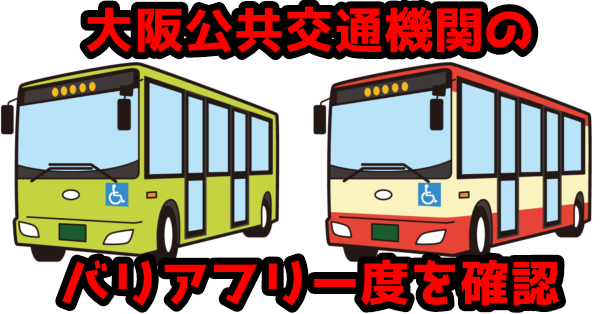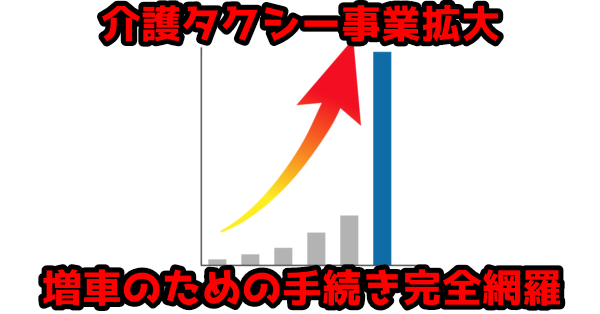
介護タクシー(福祉タクシー)を開業し、ある程度軌道に乗って、現在のお客さんを一人で回すには無理を感じてくるタイミングが来ます。
その時に検討するのが「人を雇って車を増やす」という事になります。
- 車を増やすにも許可が必要?
- 車庫を新しく借りればいい?
- 車庫はもう大きいけど車だけ増やしたい
- どんな許可が必要なの?
介護タクシーは運送業なので、新しく増やした車にも緑ナンバーを付ける必要があります。そのためには認可を受けます。
当記事では、介護タクシーの増車のための手続きの順番や、手続きの方法、手続きの申請用紙の記入法を完全網羅しています。
この記事を最後まで読むと、介護タクシー(福祉タクシー)の増車の方法、車庫の増床の方法、運輸局へ提出する書類の書き方がわかります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
介護タクシー増車、手続きの流れ
介護タクシーの場合、おそらく車庫を余分に借りている事や、事業所に空いている車庫が既にある状態はあまりないでしょう。
となると下記のような手順になります。
まず車庫を増やす必要があります。因みに介護タクシーの車庫は、普通の車庫と要件が変わりますので、詳しくは下記記事をご覧下さい。
車庫の拡大は「事業の拡大」に該当するため、認可手続が必要です。
というわけで下記は、車庫の拡大の申請手続きの解説になります。
事業計画を立て計画的に増車しよう
増車に必要なものは下記の三点です。
- 車庫
- 自動車
- 運転手
これらが揃う目処がたったら増車を計画しましょう。
車庫の拡大については「認可」をトラなくてはならないです。許可よりはハードルが低いですが、要件は満たさないと認可が下りないです。
要件は下記の項目の通りです。。
介護タクシーの認可が下りる車庫
増車には認可を受ける必要がありますが、認可が必要なのは車庫だけです。
自動車については届出でよく、運転者については増員に届出すら必要ありません。
車庫については下記の条件があります。
- 自分の土地である、または1年以上借りている
- 車がはみ出さない大きさ
- 前面道路が狭すぎない
- 水道がついている、または近くで借りれる
大きくはこの4つの条件ですが、細かい条件については下記の記事ご参照下さい。
介護タクシーの運転者に必要な条件
二種免許は絶対に必要になります。持っている人を選任するか、取りに行ってもらうかしなければなりません。
加えて、あまりないパターンではありますが「福祉自動車ではない仏の乗用車を増車する」という場合は下記の資格が必要です。
- ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
- 介護福祉士の資格を有していること。
- 訪問介護員の資格を有していること。
- 居宅介護従業者の資格を有していること国土交通省通達
介護用の設備がない場合、介護の技術を持った人が同乗する必要があります。
運転者の条件について、詳しくは下記の記事もご覧下さい。
介護タクシーの自動車の選び方
介護タクシーの営業車の条件は普通乗用車であることのみです。
- 貨物自動車
- 11人乗り以上の乗用車
上記は営業車に出来ません。
殆どの事業者さんは福祉自動車で始めると思います、後々の体力などのことを考えると福祉自動車がお勧めです。
車両の決まりについて詳しくは下記の記事もご覧下さい。
介護タクシーは特例で軽自動車でも営業ができる
なお、介護タクシーは特例として軽自動車での営業も許されています。(一般タクシーは軽自動車禁止です)
- 地域の道が狭い
- ストレッチャー需要があまり見込めない
- 最初は軽自動車で始めて様子を見たい
上記の戦略であれば軽自動車で始める事も選択の一つです。
軽自動車で始めるメリット・デメリットについては下記の記事もご覧下さい。
自動車取得のための資金計画を考えよう
開業後の増車については、資金要件がありません。運輸局から銀行残高を見られるようなことはありません。
ですが実際にお金はかかりますので、こちらも計画的に増車を行いたいです。
- 一括
- ローン
- リース
どれが得か、どれが今の事業にあっているかを考えた上で選びたいです。リースやローンについては審査もありますので、通る通らないを加味する必要もあります。
自動車購入については下記の記事にも詳しく記してあります。ご参考下さい。
なお、増車場合は業績によっては融資も考えられます。
開業前は「許可証を確認後に融資します」という金融機関が殆どですが、増車の場合は既に許可証が手元にあります。
増車の際融資を受けたいのであれば、弊所所属の「介護タクシーサポートサービス向上委員会」から融資支援担当者を紹介させて頂きます。

融資担当ご紹介希望の場合は「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
介護タクシー営業車の維持費を考える
自動車についても維持費がかかります。維持費も考慮の上で計画的に増車したいです。
- 各種自動車税
- 自賠責保険
- 任意保険
- 車検(年一回)
- 法定点検(3ヶ月に一回)
- 車庫の家賃
動かさなくても上記の維持費はかかります。動かすとさらにここからガソリン代やメンテ代がかかります。
当然ですが、軽自動車なら安く、ハイエースだと高めになります。
このあたりも考慮して計画的に増車したいです。各種維持費について詳しくは下記の記事もご参考下さい。
増車についてのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
認可申請後、最大2ヶ月の待ち時間
車庫の拡大申請については、申請後に役所での審査時間最大2ヶ月かかります。
これは役所内部の事情(標準処理期間)によるもので、ここをどう頑張っても短縮が出来ません。
なので、車は車庫の拡大申請が通ったら買う(リースする)、車庫の契約は「申請が通った時から」という契約が可能なら、やってもらうなどの工夫が必要です。
業務をやりながら車庫や車を探し、かつ許可申請の手続きを行うとなるとかなりの業務量が予想されます。
車や車庫の決定については経営案件ですが、それらが決まった後の手続き、役所との書面のキャッチボールにつきましては、ご依頼頂けましたら弊所がすべて請け負います。
介護タクシーの1台当たりの上限売上は50万とも言われていますので、1ヶ月早く増車できれば、将来の50万の売上がその分早く確保できます。
【開業前必見】介護タクシー各種申請~許可までの期間リスト@標準処理期間
お気軽にお電話、LINE、下記のフォームからメールでお気軽にお問い合わせ下さい。
介護タクシー増車手続1「申請書の入手方法」
近畿運輸局のHPでいつでもダウンロードできます。
(2)車庫の拡大・縮小(様式)
をクリックすると勝手にダウンロードされます。
エクセル形式ですので、ファイルにそのまま書き込むも良し、プリントアウトして手書きで書き込むのも良しです。
あとは空欄に名前や住所を入れていくだけです。
詳しいダウンロードや記入方法は、下記の記事をご参照下さい。
車庫拡大認可申請の作成申請を代行をご希望の場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
介護タクシー増車手続2「新旧対照表記入」
車庫を増やす前、増やした後にどうなるかを新旧対照表にして提出します。
車庫については令和5年10月31日より「自動車の大きさ+前後左右50cm」のルールがなくなり、自動車がはみ出さない車庫なら認可がおりるようになりましたので、増車がしやすくなりました。
尚、車を同時に増やす場合は、この時点で車の台数も増やしておきます。
具体的な記入例については、下記の記事をご覧ください。
介護タクシー事業変更申請3「事業計画新旧対照表」書き方
介護タクシー事業変更申請4「営業車の新旧対照表」書き方
介護タクシー増車手続3「幅員証明書」
車庫を増やす場合には、車庫の前面道路が規定に足りている事を証明する為に、前面道路の幅員証明書を役所で取得して添付します。
前面道路の道幅については、原則
(車幅✕2)+0.5m
があれば許可が通ります。
それ以下の道幅の場合でも、既に車庫として使われていた実績がある場合は、例外規定が適用になる可能性がありますので、ぜひ弊所にご相談下さい。
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
尚、幅員証明取得の具体的な手続については、下記の記事をご覧ください。
介護タクシー増車手続3.5「幅員証明書が廃止された自治体の場合」
大阪では大阪市等1/3程度の自治体で幅員証明書の発行を廃止しています。
自治体に幅員証明がない場合は「前面道路の宣誓書」を提出します。
「宣誓と違っていたことが発覚したら、許可取り消しても文句言うな?」という旨の宣誓となります。
宣誓の場合、実際に現地で測定をするか、建設局等から市街図を取り寄せて調べる必要があります。
現地測定等、かなり時間が取られますが、測定についても弊所で請け負うことが出来ます。
詳しい作成方法は、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー事業変更申請5.5「幅員証明が無い場合は宣誓書」書き方
車庫拡大認可申請の作成申請を代行をご希望の場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
介護タクシー増車手続4「各種宣誓書」
建物関係の宣誓書
車庫が建物である場合は、建物が
の各法に違反していないという宣誓書を書きます。
宣誓書なので証拠書類の提出は求められませんが、発覚した時には許可取り消すけど文句を言うなという旨の宣誓書になるので、調査しておいて損はありません。詳しくは下記の記事まで。
他の運送会社の役員ではない宣誓書
運送業は、過去に運送業を経営していてやらかした人はしばらく運送業を経営出来ないという決まりがあります。
他の運送会社の役員であってもいいのですが、その場合、過去に処分等を受けた運送会社の役員であることが発覚したら許可取り消しまであります。
処分等受けた運送会社の役員をやっていると、一定期間運送業を開業出来ず、他の運送会社の役員にもなれない決まりがあるからです。
尚、具体的な記入方法や、適用される処分の内容については、こちらの記事をご参照下さい。
増車したら任意保険に入る宣誓書
増車を伴う車庫拡大の場合は、同時に提出します。
増車したら増車した車の任意保険には必ず入る宣誓書です。
許可の時は見積書の提出も必要でしたが、変更申請の時は、宣誓書だけで良いです。
任意保険には必ず入るようにしましょう。
上記の3枚の宣誓書について、詳しい記入法や意味については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー増車手続5「必要添付書類」
下記の書面を申請書と同時に提出します。
弊所では添付書類収集も代行させていただいております。下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
見取り図、平面図
車庫を拡大する場合は、車庫の見取り図平面図が必要です。
面積がわかる寸法図、写真撮影をした場合は矢印を記入等必要です。
実際に写真を取ったり測定を行わなければならないので、ここが一番手間です。
営業所や休憩所に変更がない場合は、平面図や写真は許可申請時の物をそのまま流用すればOKです。
不動産登記簿謄本
新しい車庫や営業所が、自分の持ち物である場合は、不動産登記簿謄本を取り寄せて添付が必要です。
登記簿は法務局ですぐ取れますし、ネットでも郵送でも取れます。ネットで申請すると、登記簿が家に届きます。
尚、登記簿は住所ではなく「地番」がわからないと取り寄せられないので、地番を調べる必要があります。
地番は、法務局に聞けば教えてくれたり、法務局が運営する「地番検索サービス」等で調べることが出来ます。
賃貸借契約書
営業所や車庫を借りる場合は、賃貸借契約書が必要です。
契約書が必要という事は、申請前に契約はして置かなければなりませんが、未来の日付や「申請が通った時から」等の契約方法でも許可は下ります。
申請日から1年以上借りている必要があります。
各種写真
営業所・休憩所
- 建物全景
- 出入り口
- 部屋全体
車庫
- 専有部分
- 車庫全体
- 前面道路を挟んだ出入り口
- 前面道路を左右方向から
- 専有部分から出入り口までの通路
これらの撮影を行います。どれをどこから撮った等を平面図に矢印で書込み、番号を振ります。
増車申請に必要な添付書類については下記の記事をご参照下さい。
以上が車庫拡大・増車の申請の手続きとなります。
尚、既に車庫にもう何台か営業車が止められる余裕がある時は「増車届」という届出だけですみます。
介護タクシー増車手続6「増車届の入手方法・表紙の記入」
車庫が既にあって、増車のみ届出る場合は、手に入れる書面が違ってきます。
入手法は車庫拡大と同じく近畿運輸局のHPで入手します。
(3)増車・減車(様式)
をクリックすると勝手にダウンロードされます。
ダウンロード、入手法について、詳しくは下記の記事をご覧下さい。
新旧対照表
変更前、変更後に営業車の台数がどうなるかの詳細を示した対照表を提出します。
申請書に様式があるので、書き込むだけです。
これがメインの書類です。
任意保険に入る宣誓書
上記にもありますが、増車のみの届出の場合もこれを提出します。
任意保険には必ず加入するようにしましょう。
現在の車庫の収容能力を申請
現在の車庫の収容能力(面積と台数)と住所を記入した書面を提出します。
令和5年10月31日から「自動車の車長車幅+前後左右50cm大きい」というルールがなくなり、自動車がはみ出さない車庫なら認可が下りるようになりました。
面積については、車の車長車幅の面積と照らし合わせた上で、確認して書面を出すようにしましょう。
既存車庫で認可を受けた収容台数の扱い
令和5年10月31日から「自動車の車長車幅+前後左右50cm大きい」がなくなり、小さい車庫でも認可が下りるようになりました。
これより以前に許可や増車の時の認可に収容台数を書いて申請をしていると思いますが、新ルールだと既存2台の所に3台置ける様になるパターンが少なくありません。
この場合2台の所を3台として再度認可を受ける必要はありません。面積が足りていれば増車を運輸局では増車を受け付けてくれるとのことです。収容台数はあくまで目安、面積で増車を受け付けると運輸局からの回答です。
添付書類
大まかに下記の物が必要です
・既に認可を受けている車庫の位置、収容能力がわかる書面
車庫に余裕があればいいですが、余裕が無い場合は添付書類について詳細が求められますので、書類が増えます。
このあたりの運輸局への対応は是非弊所にお任せ下さい。
尚、増車届の具体的な記入例に付きましては、下記の記事をご参照下さい。
以上が増車手続き完全網羅になります。
車庫拡大認可申請の作成申請を代行をご希望の場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
増車用の車庫や車が許可が取れるか不安だったら
運輸局等の役所では、条件だけ口頭で伝えても法律に即した原則でイエス・ノーしか答えてもらえません。
ですが、実際の物件の具体的な住所や建物、車庫の様子などを写真撮影、測定等を行い、それを実際に役所に持ち込むことで改善点の助言などが貰えたりします。意外と少ない改善点で許可物件になることもあります。
行政書士はそのあたりの交渉を得意としています。希望物件が怪しいと思ったら是非下記のメールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。
LINEでのご相談は無料です
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。
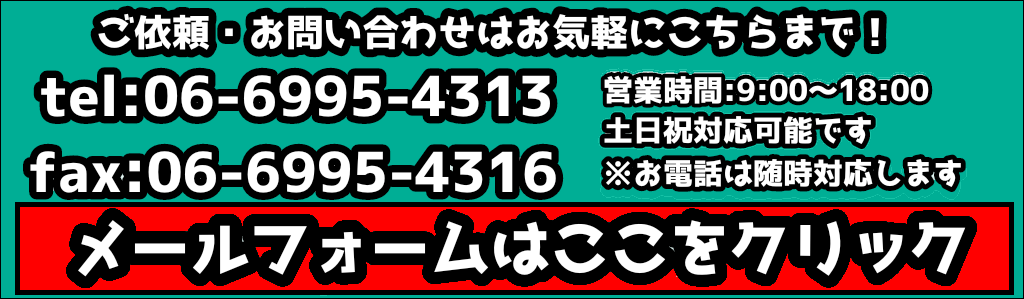
メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)