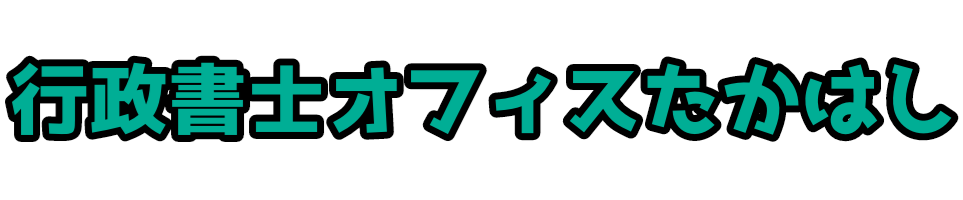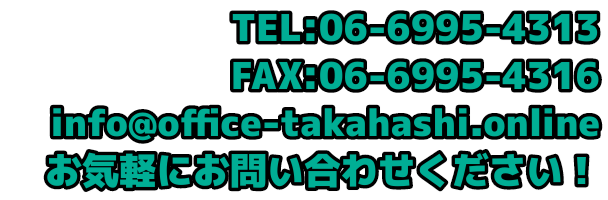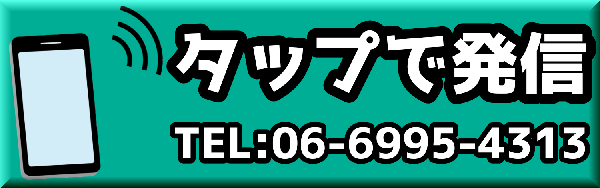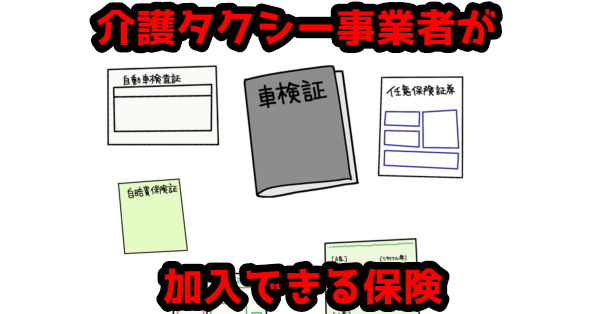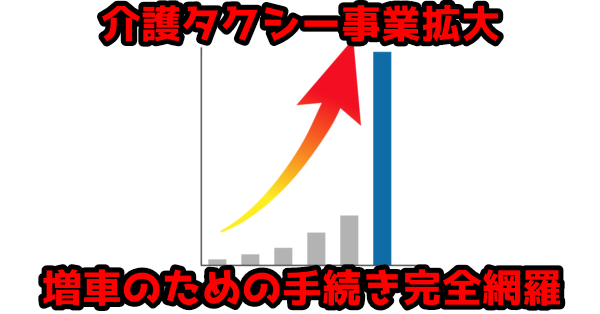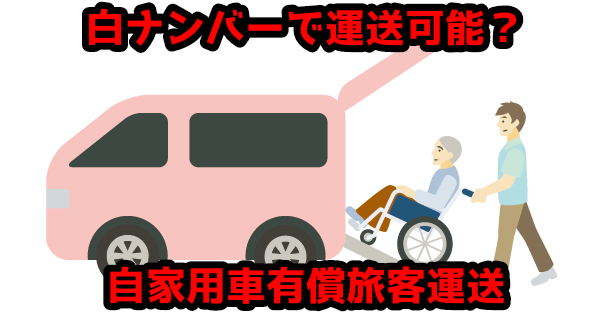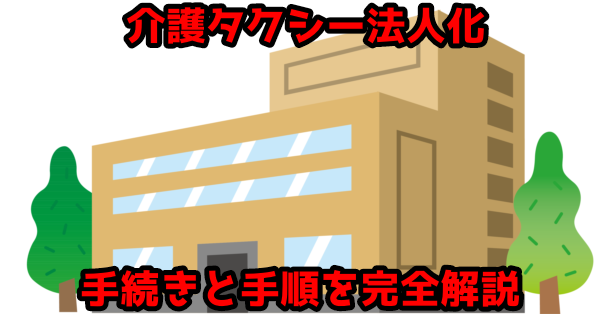
介護タクシー(福祉タクシー)を順調に運営し、営業車の台数や雇用する人数も増えると
「そろそろ個人事業でも限界かな、でも法人化って度のタイミングでしたらいいの?」
という壁にぶち当たります。
- 売上1000万超えたら(消費税の関係)
- 雇う人が5人を超えたら(社会保険の関係)
いろんな基準があります。では
- 法人化の手続はどうやったらいいの?
- 個人事業で取った運送業の許可は?また取り直し?
当記事は、個人事業で取った運送業許可を、法人化の後にも継続できる方法を解説します。
行政書士オフィスたかはしは役所への申請、なかでも介護タクシー(福祉タクシー)の開業許可を専門として行っており、この申請を代行する事が可能です。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
法人化のメリット・デメリット
法人と個人事業ではメリットとデメリットがあります。
メリットについては一般的に下記の事が言われています。
- 一定以上の売上から法人の方が税金が安くなる
- 事業主が亡くなっても存続できる
- 経費の幅が広がる
- 人を雇いやすくなる
- お金を借りやすくなる
デメリットは下記の通りです。
- 赤字でも一定の税金が取られる
- 従業員1名以上いれば社会保険加入
- 会計処理が自分の手に負えなくなる
- 法人設立に資金が必要
売上1,000万以上になってくると法人の方がメリットが高くなり始めると言われています。
これを検討するような売上になっている頃にはもう税理士が入っていると思います。
介護タクシーの場合の法人化検討タイミング
介護タクシーの場合は主に下記のタイミングで検討をすると良いです。
- 従業員が5人以上になった
- 営業車が5台以上にしたい
営業車を5台以上にするにあたり、介護タクシーの人事はガラリと変わります。
国家資格者の雇用などもしなければならなくなりますので、法人化をしておく方が利便性が上がってきます。
なお、5台以上にしたい時にしなければならない事については下記の記事もご参考下さい。
5台以上にする時に国家資格者が2名必要
前項目で書きましたが、5台目を増やそうとする前に国家資格者が2名必要です。
- 運行管理者
- 3級以上の整備士or2年以上の自動車整備実務経験者
上記の方を雇おうというときに、個人事業主だと知り合いくらいしか来てくれない可能性が高いです。
知り合いに居ない場合は、法人化して法人として人員の募集をかけた方が応募の可能性は高いです。
なお、運行管理者および整備管理者の資格要件について詳しくは下記の記事もご参考下さい。
整備管理者の資格要件について詳しくはコチラ
運行管理者の資格要件について詳しくはコチラ
事業譲渡は新規許可取得より手続きが煩雑になる
今受けている許可番号を活かしたいどうしてもの理由がなければ、法人で新規許可を取ったほうが良い場合も多いです。
今ある設備や施設、人員を会社の持ち物にする契約の整理をしなくてはなりません。
- 雇用契約の結び直し
- 施設の個人→法人への譲渡
- 施設の個人→法人への賃貸借契約
- 施設が賃貸の場合は法人で契約し直し
- 新しい物件の調達
- 保険などの法人名義での契約し直し
対外契約については法人名義で結び直し、個人の持ち物は法人へ譲渡、譲渡したくない物は個人から法人へ賃貸借契約、貸したくもない物は法人で新しい施設を用意。
開業の要件を満たせる状態にして事業を譲渡します。
介護タクシー法人化の場合の事業譲渡のメリット
新規よりかなりやることが多いですが、下記のメリットがあります。
- 今受けている許可番号を引き継げる
- 資金チェックがない
許可番号については、それを見ている利用者はほとんど居ないのでメリットであるとは言えないかもしれません。
一番のメリットは「資金チェックがない」ということです。
新規許可の場合は、銀行残高を運輸局にチェックされます。ある程度まとまった残高がないと許可が取れません。
事業譲渡は、物件や人員を移転して要件を満たせれば良いので、資金チェックがありません。
ここにメリットを感じる場合は多少手続きが多くても、事業譲渡を検討してみて下さい。
介護タクシー法人化への流れ
法人化する手続きを大まかに言うと下記のようになります。
個人で経営していた事業を設備ごとまるっと法人に譲渡します。
施設等の譲渡は「事業譲渡の認可が下りた時」という条件付きで契約書を交わすとスムーズです。
営業権だけを譲渡は出来ません。運送業は施設設備、人に許可要件がついているので、施設や人ごと事業を譲渡しなければ許可が継続できません。
もし、譲渡をしない設備があるのであれば、新法人で許可の取れる別の設備を用意しなければいけません。
介護タクシー法人化手続き1「会社の設立」
まずは会社を作ります。どんな法人でもOKです。介護タクシーの法人形態に制限はありません。
- 株式会社
- 合同会社
- NPO法人
このあたりが代表的です。
定款に「運送事業を行う」という旨の記載を必ずしておきましょう。
既存の法人を使ってもOKです。その際には定款を書き換えて「運送事業を行う」という旨の記載を加えましょう。
介護タクシー法人化手続き2「法人と個人で介護タクシー事業の譲渡契約」
個人と法人間で事業を譲渡する契約書を作成します。
それに伴い個人事業で使っていた営業車、営業所、休憩所、車庫等の譲渡契約を交わします。
この時「譲渡譲受認可申請が下りた後」という条件付きで契約書を作成し、まだ譲渡は行いません。この時に
- 自己物件の場合は個人から法人に譲渡する
- 譲渡する金額もこの時に決めておく
- 賃貸借契約の場合は、法人名義で借り直す
- 自宅兼営業所等、法人に譲渡できない物件は整理し、新しく営業所を借りる、個人から法人に賃貸借契約を交わす
等の整理が必要です。法人化を期に事業と個人の資産をしっかり分けておく事をお勧めします。
法人に個人の持ち物をいくらで譲渡するかも、譲渡譲受認可申請に添付しますので、この時に決めておく事が必要です。
尚、契約形態に付きましては弊所でもご相談承っております。

LINEでのご相談は無料です
介護タクシー法人化手続き3「譲渡譲受認可の申請」
譲渡する物件、譲渡する金額が決まれば認可申請が提出できます。
この時に
- 事業譲渡譲受認可申請書
- 自動認可運賃申請書
を同時に運輸局に出します。
事業の許可は譲渡して継続ですが、運賃の認可については改めて得ておく必要があります。
自動認可運賃を選ぶと、特に問題なく1ヶ月程度で認可がおります。
認可が下りてから出すと、1ヶ月タイムラグが生まれるので、忘れずに出しておくようにしましょう。
譲渡譲受認可申請書の入手、記入方法
申請書の入手方法
申請書は下記のリンクから手に入ります。
3.事業の譲渡譲受(法人成りを含む)を考えている方はこちら
の下にある「申請書(様式)」をクリックすると自動でダウンロードされてきます。
表紙等は名前や住所を書くだけになりますので、そのまま記入して下さい。
詳しい申請書の入手方法については、下記記事をご参照下さい。
新旧対照表
事業を譲渡する前と、譲渡した後に事業計画(営業所・休憩所・車庫)がどう変わったかを譲渡人、譲受人両方の立場の新旧対照表で提出します。
営業所・休憩所・車庫がどう変わったか
営業車がどう変わったか
上記の2枚を書いて出します。
具体的な記入例については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー法人化手続き3「事業計画新旧対照表」書き方
介護タクシー法人化手続き4「車両数新旧対照表」書き方
運行管理体制表
運行管理体制表を記入します。これは、新規許可申請時に提出していますが、法人化にあたり再度提出します。
等は、もうこの時点では決まっていると思いますので、今まで通り就いていた人を書き込みます。
運行管理者と運転者の所に同じ人の名前が無いようにだけ注意して下さい。
運行管理体制表の具体的な記入例については、下記の記事をご参照下さい。
主要人事の就任承諾書
下記の主要人事について
認可が下りた暁には、誰を就かせるかを書いて提出します。
運行管理体制表と整合性が取れるように、同じ人の名前を書くようにしておいてください。
ここも、運転者と運行管理者の所に同じ人の名前が書いていないように注意して下さい。
尚、各就任承諾書の記入例については、下記の記事をご参照下さい。
役員名簿
法人化した際に法人の役員を決めているはずなので、その名簿を提出します。
特に難しい所はありません。
幅員証明書or前面道路の宣誓書
現在使用している車庫全ての前面道路の幅員証明書を添付します。
大阪では約1/3程度の自治体が幅員証明書の発行を廃止しており、その場合は「前面道路の宣誓書」が申請書に付いているので、道路を実寸して寸法を書き込み、添付します。
役員名簿や前面道路の宣誓書の具体的な記入例については、下記の記事をご参照下さい。
介護タクシー法人化手続き8「幅員証明書」書き方
介護タクシー法人化手続き8.5「前面道路の宣誓書」書き方
介護タクシー法人化手続き4「必要添付書類を集める」
既存会社への譲渡の場合の添付書類
- 事業譲渡契約書のコピー
- 譲渡及び譲受価格の明細書
- 定款、寄附行為及び登記事項証明書
- 最新年度の貸借対照表
- 役員及び社員の名簿、履歴書
会社設立前の場合
- 定款(設立前に作っておく)
- 譲渡譲受契約書(法人設立時に効力開始の条項を入れる)
- 発起人、社員または設立者名簿、履歴書
- 株式の引受状況の見込みを記載した書類
定款については設立前でも必要になりますので、登記を依頼する予定の司法書士先生に前もって作って貰う事がお勧めです。
施設関係
- 案内図、見取り図、平面図
- 営業所、休憩所、車庫が2km以内であることを証明する地図
- 共同車庫の場合は車庫の全体図
- 登記簿謄本(自己所有の場合)
- 賃貸借契約書のコピー(申請日から1年以上借りている)
写真撮影
- 営業所・休憩施設の建物全景、出入り口、部屋全体の写真
- 車庫は専有部分、車庫全体、前面道路を挟んだ出入り口の写真
- 前面道路の左右方向の写真
- 共同車庫の場合は専有部分から出入り口までの通路も撮影
- 写真を撮影した方向を矢印で施設図に書き込む
尚、法人化に伴う事業譲渡譲受認可申請の必要添付書類について、詳しくは下記の記事をご参照下さい。
以上が、法人化手続の徹底解説となります。
法人化で何から取り組んでいいかわからない時は
まず現状の状態をヒヤリングします。その上で、何が足りなくて何を異用意すればいいのかについて、チェックリスト方式でアドバイス出来ます。
会社の設立、譲渡契約、事業譲渡認可の代行については行政書士が得意としている所です。下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEでのご相談は無料です
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。
LINEでのご相談は無料です
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。
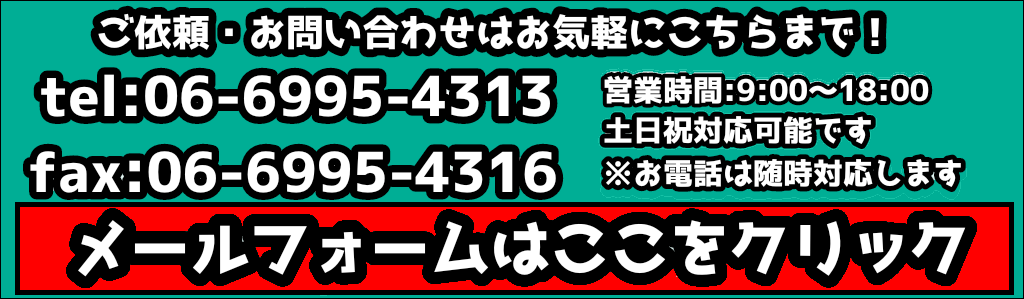
メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)