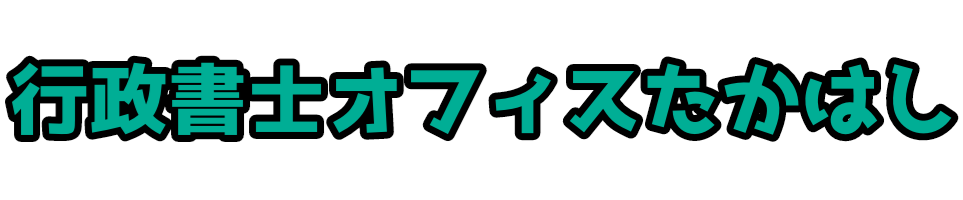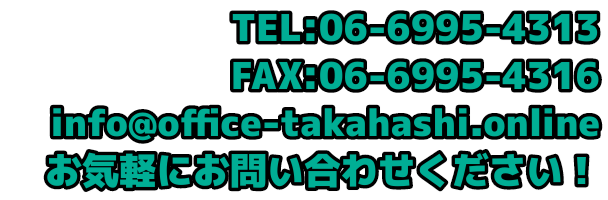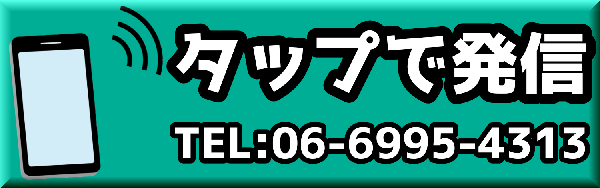介護タクシーを始めるに当たって許可を受けますが、許可内で必ず守らなければならない法律があるのをご存知でしょうか?
- どんな法律なの?どんな決まりがあるの?
- 守らなかったらどんな罰があるの?重たいの?
法律は「知らなかった」で罰を免れる事ができません。
そこで当記事では、特に重たい罰がある違反、こんな時に罰則があるなど「これだけは覚えておけ」という大枠の部分を解説したいと思います。
どんな時に罰則があり、特にどの様な時に罰則が重いのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、運送業が罰金や営業停止、懲役になるような時はどんな時かがわかります。
このような、開業後に必要な情報についてはネット上にあまりありません。弊所でまとめましたので、下記の記事もご参考下さい。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
LINEでのご相談は無料です
介護タクシーを開業できない条件「欠格事由」
介護タクシーを開業するに当たって一番最初に触れる法律が「欠格事由」となります。
欠格事由に当てはまっている人は、そもそも介護タクシー及び運送業を開業することが出来ません。
営業許可申請時に「欠格事由に該当していません」という宣誓書を書かされます。該当していたことが発覚した場合、炬火が取り消されても文句は言えませんという内容になります。
下記のような宣誓書を書きます。もし該当している場合は、自分は経営陣から外れましょう。5年経てば事業者になることが出来ます。
介護タクシー許可申請書の欠格事由宣誓書について詳しくはコチラ
道路運送法第7条(欠格事由)
道路運送法第7条(欠格事由)
道路運送法7条より抜粋
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
道路運送法は運送業全てにわたる法律なので、これに該当すると介護タクシーどころか一般タクシー、ハイヤーも許可が下りません。全部で8項目あります。
禁錮または懲役から5年
一、許可を受けようとする者が一年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者であるとき。
道路運送法第7条1項1号
色んな法律に「禁錮以上」ってフレーズがよく出てきますので整理しておきますと
死刑>懲役>禁錮>罰金>勾留>科料
の順番です。ここでの問題は実質懲役と禁錮です。
運送業で特に気をつけなければならないのは交通関係です。過失運転致死罪は禁錮の可能性、飲酒運転は下手すれば懲役の可能性があります。
法律によると禁錮懲役が終わってから5年は開業ができません。尚、執行猶予の場合は「執行猶予期間が終了したときは、刑の言い渡しそのものが失効する」という扱いになり、執行猶予終了の翌日から介護タクシーの開業申請を行うことが出来ます。
かつて運送業で取消を受けた人
二、許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業または特定旅客自動車運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から5年を経過していない者。
道路運送法第7条1項2号
かつてタクシーなどの旅客運送業の許可を受けて営業し、なんらかの理由で取消を受けた人は、取り消しを受けてから5年以内は新しく許可をもらうことができません。
かつて運送業許可取消を受けた人が実質支配する体制
三、許可を受けようとする者と密接な関係を有する者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、もしうくはその事業に重要な影響を与える関係にある者が、一般旅客自動車運送事業または特定旅客自動車運送事業の許可の取消を受け、その日から五年の経過をしていない者であるとき。
道路運送法第7条1項3号
妙に条文が長いですが、なるべく簡単にすると・・・。
許可を申請する人を実質的に支配する人(株主や出資者など)が前項の「かつて運送業で取消を受けた人」に該当している場合です。すごく端折って説明しますが
- 議決権を半分以上持っている人
- 持分会社(合同会社など)の資本金を半分以上出資している人
- 親会社の議決権を半分持っている人
- 親会社が持分会社の場合、その資本金を半分以上出資した人
- それと同等の支配力を持っている人
詰まる所、かつて運送業許可の取消を食らった人が、新しく子会社を作って出資、言うこと聞く人を代表にして申請をさせるという事はダメということです。
逆に、許可を受けた人の下で働くということは妨げはありませんが、実質支配してしまわないようにしましょう。実質支配している体制のままでは、介護タクシーの開業が出来ません。
聴聞通知を貰って処分の日までに廃業した人
四、許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業または特定旅客自動車運送事業の許可の取消の処分にかかる行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に第三十八条第一項もしくは第二項又は第四十三条の規定によ事業の廃止の届け出をした者で、当該届出の日から五年を経過していないものである時。
道路運送法第7条1項4号
許可の取り消しというのはいきなりされません。まず聴聞通知という「お前の許可取り消すつもりだけど、なんか申し開きはあるか?」というお知らせが来ます。
反論があれば聴聞で自分の主張を行います。
しかし、取消における聴聞の通知が来て、聴聞の前に廃業したから取消になっていないのでセーフ!というわけにはいかないという条文です。
この聴聞の通知が来た時点で欠格期間は免れない考えるのが正しいかもしれません。言い分があるなら聴聞でちゃんと主張した方がいいです。
この場合、欠格期間のスタートは廃業届の日になります。欠格期間が終わるまでは介護タクシーの開業は出来ません。
検査・報告の結果、聴聞が決まった日までに廃業届を出した
五、許可を受けようとする者が、第九十四条第四項(報告、検査及び調査)の規定による検査が行われた日から聴聞決定予備日までの間に第三十八条第一項もしくは第二項又は第四十三錠第八項の規定による事業の廃止の届け出をした者で、当該期間の届け出の日から五年を経過していない者であるとき。
道路運送法第7条1項5号
この条文はつまるところ
という流れで、廃業した人についてはやはり5年間、新規でタクシーの営業許可を出せないということです。
やはり、聴聞通知が来た時点で欠格期間は免れないということです。
聴聞通知を貰う前60日以内に役員をやっていた
六、第四号に規定する期間内に第三十八条第一項(事業の休止及び廃止)もしくは第二項又は第四十三条第八項(特定旅客自動車運送事業の休止廃止)の規定による事業の廃止の届け出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の通知の日の前六〇日以内に当該届出に係る法人の役員であったもので、当該届出の日から五年を経過していないもの。
道路運送法第7条1項6号
4つ目の「聴聞通知を貰って処分の日までに廃業した人」の、廃業届を出した日より前60日の間に、その法人の役員をやっていた人は、5年新規開業できません。
聴聞通知が来たのに、聴聞もせずに廃業しちゃった!というパターンは、結構悪質と取られるので、廃業を届けた日からさかのぼって60日の間にその法人の役員だった人までアウトです。
廃業届の日から5年は新規タクシーが立ち上げられません。
未成年が開業する場合、その保護者が欠格要件に当てはまっている
七、許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く)又は次号の・いずれかに該当する者であるとき。
道路運送法第7条1項7号
介護タクシーは未成年も開業できますが、今回8項目のうち3以外の7項目のどれかに保護者が当てはまっているとアウトです。
役員の場合ならその人を別のポジションにすればいいですが、法定代理人はほぼ親なので変えられません。つまり子供が成人するか、親の欠格期間が解けるかまで介護タクシーの開業は待たなければなりません。
法人の場合、役員に就く人がどれかに当てはまっている
八、許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号におのいずれかに該当する者であるとき。
道路運送法第7条1項8号
法人の場合は申請を行う代表の人だけではなく、役員の人もこの要件に当てはまっていると許可が下りません。
役員については、欠格期間が終わるまで役員から外れてもらい、実質支配できない体制にしておく事で開業自体は可能です。
人事を考え直す、新しい人を探す、期間が明けるまで待つなど、余計な時間と手間が増えます。なるべくそういった事は避けたいです。
法令遵守について詳しく知りたい、自社の法令遵守を整えたいなどのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
LINEでのご相談は無料です
介護タクシー開業時に守る事を宣誓する「法令遵守」
介護タクシー開業時に下記の文言が書いてある宣誓書にサインさせられます。
1,一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の審査基準についての11、法令遵守(3)(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)の規定に抵触いたしません
2,万一上記と相違した事実が判明したときは、何時許可の取消処分を受けても異議を申しません。
近畿運輸局介護タクシー営業許可申請書より引用(PDF)
つまり、これらに該当している人でないと後からバレた場合は、即刻許可の取り消しをされても文句は言えないという宣誓です。
しかし条文番号だけで内容が書いていません。内容について詳細は下記で解説させていただきます。
(3)役員をする人は以下8項目に該当していること
(3)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員↓が、次の(イ)~(チ)の全てに該当する法令遵守の点で問題ないこと。
近畿運輸局審査基準より抜粋
(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)
役員は、以下8項目に反していてはいけません。役員、顧問、相談役みたいな役員に相当する肩書の人もそれに含まれます。では1項目ずつザッと行きます。
(イ)(ロ)(ハ)昔処分を受けた人は一定期間役員になれない
道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法に違反して下記の処分を受けた者ではないこと。
・申請日3ヶ月前~申請後50日後の間に
50日以下の施設の使用停止、制限、禁止の処分を受けた者ではないこと。
・申請日6ヶ月前~申請後50日後の間に
190日以下の施設の利用停止、制限、禁止処分を受けた者ではないこと。
・申請日前1年~申請日以降
190日を超える施設の利用停止、制限、禁止処分を受けた者ではないこと。
要は重たい処分を受ければ長い間役員になれません。1年間違反をしていない人を役員にすることが確実で安心です。
(ニ)業務改善命令を受けて、改善が終わっている
道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法の違反により
- 輸送の安全の確保
- 講習の利便を阻害する行為の禁止
- 公共の福祉を阻害している事実
等に対して改善命令を受けた場合、申請日前に改善が済んでること。
(ホ)重大事故を起こしていない
申請日前1年~申請日以降に自分が原因の重大事故を発生させていないこと。
重大事故の例は下記になります。
- 10人以上が負傷
- 10台以上の車が絡む
- 死者重症者が出る
他にもかなりの種類があります。
(ヘ)悪質な道交法違反がない
申請日前1年~申請日以降に、悪質な道路交通法の違反がないこと。
- 酒酔い運転
- 酒気帯び運転
- 過労運転
- 薬物等使用運転
- 無免許運転
- 無車検(無保険)運行
- 救護義務違反(ひき逃げ)
(ト)各種報告書をちゃんと出している
旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則、自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
決算につき提出する書類や、事故の報告、運送実績等を前の運送業でしっかり出していない場合は、介護タクシー事業者や役員になれないことになります。
(チ)営業の停止命令、取消命令を受けた者ではない
過去に運転代行業をやっていて、申請日の2年前~現在までに違反により営業の停止、廃止、取消の命令を受けた。
イ、ロ、ハ、ニ、ト、チについては、過去~現在にかけて運送業を営んだことがある方のみ気をつけて下さい。健全経営で1年営んでいれば、新しい運送業の役員になれるということです。
ホ、ヘについては道交法違反なので、運送業を営んでいなくても該当する場合があります。飲酒運転や、自賠責保険切れなんかには要注意です。
次回は就任承諾書です、各ポジションに誰を就任させる予定かを書いて提出します。
記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
LINEでのご相談は無料です
介護タクシー事業の罰則のある違反
介護タクシーの事業者が守らなければならない法律は主に下記の通りです。
- 道路運送法
- 道路運送法施行規則
- 旅客自動車運送事業運輸規則
- 国土交通省通達
- 運輸局の審査基準
勿論これ以外にも守らなければならない物はありますが、事業にまつわる法律、通称「業法」は主に上記の通りです。
そして、これらに違反すると罰則がある物があります。どんな時に罰則があるかを覚えておいて、違反しないようにしましょう。
勿論、罰則がない物を守らなくていいというわけじゃないです、法令遵守です。
無許可営業
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
道路運送法第4条より抜粋
3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、その併科。
無許可営業すると懲役まで付きます。道路運送法の罰則でも一番重いです。当然ですが、運送業を行う場合は運輸局の許可を取りましょう。
料金の無認可
料金の認可を受けないで、または認可を受けた料金によらないで、運賃又は料金を収受した時
道路運送法第98条を要約
100万円以下の罰金。
運賃も認可を受けなければなりません。タクシーは激安競争が起こらないように法律が決められているので、認可運賃以外で旅客を運ぶと罰則です。
運賃料金の割戻し
100万円以下の罰金。
乗客から受けた運賃料金を一度受け取っておいて一部返したりするのもアウトです。
前項と同じく、安売り競争が起こらないようにされていますので、安売りを促すような事については厳しく罰則があります。
運送約款によらない契約
運送約款の認可を受けないで、または認可を受けた運送約款によらないで運送契約を締結した時
道路運送法第98条より抜粋
100万円以下の罰金です
運送約款には運賃料金も書いてありますので、これ以外の料金で旅客を運んではいけません。料金以外の条項も無視すると罰金です。
運送約款、料金運賃の公示義務
運賃、料金、運送約款は車内の見やすい所に公示しなければなりません。運送約款はホームページ等に公示でもOKだそうです。
公示義務を怠ると100万円以下の罰金です。
事業計画変更の申請義務
車庫の拡大や施設の移動、増車、重要人事の変更等は運輸局に届出なければなりません。
届出を怠ると100万円以下の罰金です。
事業計画は下記の記事をご覧ください。この書面に書いたものについては、変更する時に申請が必要と考えて間違いないでしょう。
営業区域外の旅客を運送
営業区域は都道府県単位です。大阪だと、大阪発または大阪着どちらでもいいのですが、発着が両方とも他県の旅客を乗せると罰金です。
100万円以下の罰金となります。
安全管理規程を定め、国交相に届ける
介護タクシーではあまりありませんが、200台以上の規模の事業者は「安全管理規程」を作成し、国土交通大臣に届ける義務があります。
義務を怠ると100万円以下の罰金です。
改善命令に従わない時
- 不当な運送条件によることを求め、公衆の利便を阻害する行為
- 不当な競争。
- 特定の旅客に対して不当な差別的取扱い
上記三点が発覚した時には国土交通大臣は改善命令が出来、それに従わない場合は罰則です。
改善命令は主に下記の通りです。
- 事業計画を変更する
- 運賃の上限を変更する
- 運賃又は料金の変更
- 運送約款の変更
- 自動車その他の輸送設備を改善する
- 旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずる
100万円以下の罰金になります。
事業貸し、名義貸し
自分が許可を得た事業を他人に営業させるような事業貸しについては罰則です。これは無許可営業と同じくらい重い罰則があります。
3年以下の懲役、300万以下の罰金、その併科。
委託受託を無許可で行う
事業の委託受託は出来ますが、国交相から許可を受けなければ無許可です。
無許可の場合は1年以下の懲役、150万以下の罰金、その併科です。
休止廃止届をしないで事業を休止廃止した
無届けの場合は罰則があります。
100万円以下の罰金となります。
事業停止取消命令に従わなかった
1年以上の懲役、若しくは150万以下の罰金、これを併科。
営業許可を取る前に営業許可申請をしますが、その申請書通りに事業を行わない場合には、事業休止や取消命令が下る事があります。
車庫や営業所休憩所の位置、営業車、人事等を許可が下りた通りに行わないと許可取り消し命令が下り、それに従わないと罰則です。
刑事罰以外の違反と罰則について
上記は業法違反に関する刑事罰を挙げましたが、介護タクシーはこれ以外にも違反があります。
刑事罰まで行かない交通違反があるように、刑事罰まで行かない運送業法違反が、介護タクシーに関連する物だけで約200程度あります。
懲役や罰金はありませんが
- 勧告
- 警告
- 営業車使用停止◯◯日
- 事業停止
- 許可の取り消し
などの処分が行われます。詳しくは下記の記事もご参照下さい。
許可に関する違反には罪が重い
以上が道路運送法と関連法規の主な罰則でした。
道路運送法は、運送業の許可に関する事が書いてある法律なので、特に無許可や名義貸しなどの罪は重いです。懲役まであるので、くれぐれも違反しないようにしましょう。
罰金は前科にはなりませんが、懲役は前科になります。禁錮以上の罪は、運送業以外の他の営業許可についても欠格要件になっている事が多いので、くれぐれも許可を取り、許可の通りに運営するようにしましょう。
罰則等が知りたいなどのご相談については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
LINEでのご相談は無料です
介護タクシーで守るべき決まりがわからない時は
- 道路運送法がどういう法律かちゃんとわかっていない
- 何に注意すればいいのかわからない
- どういう罰則があるのかわからない
- 今の自分が開業できるか知りたい
等、法令についてよくわからない場合はご相談ください。行政書士は道路運送法などの業法については得意としております。
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
LINEでのご相談は無料です
まとめ
- 道路運送法の違反にも罰金や罰則がある
- 無許可や名義貸しは懲役もある
- 1発罰則の物もあれば、改善命令違反まで罰則がない物もある
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。
LINEでのご相談は無料です
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。
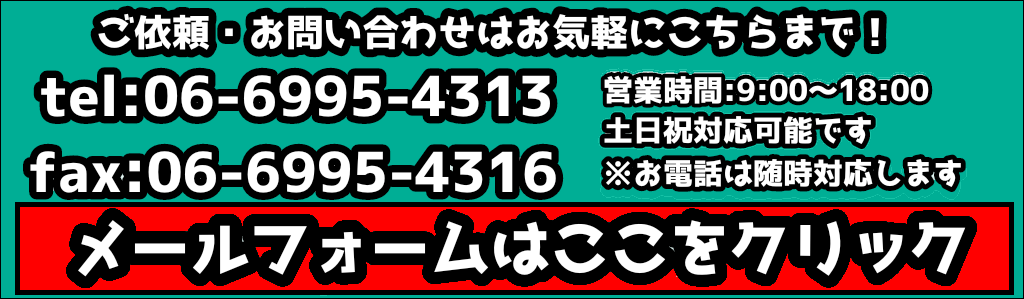
メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)