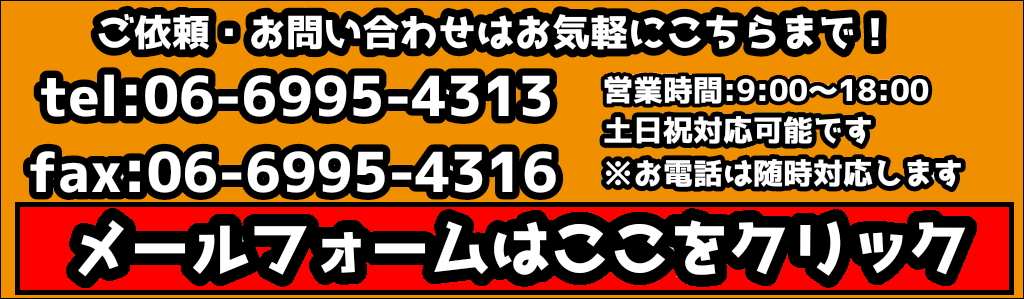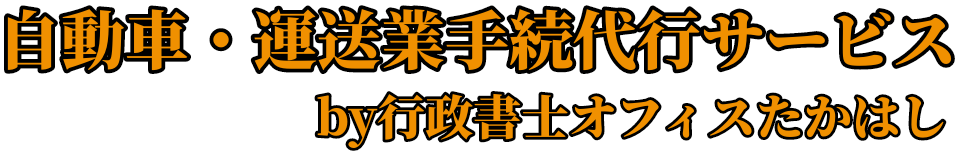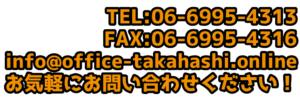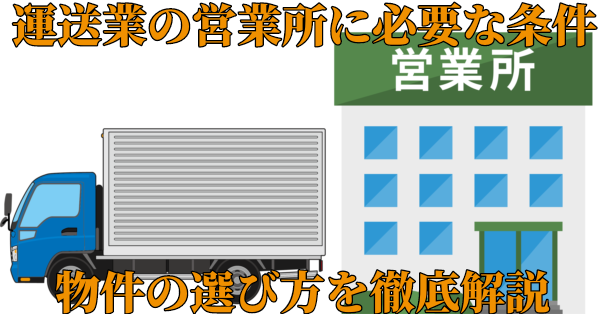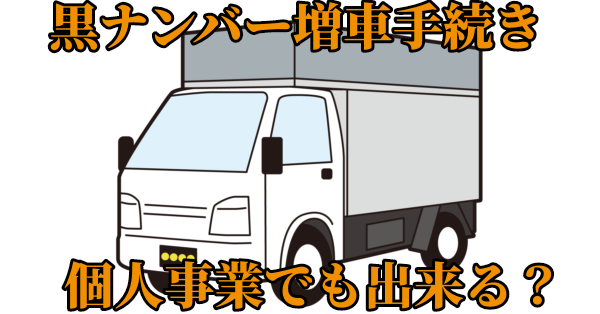霊柩車も実は運送事業の一種です、運送事業ということは当然許可が必要です。
運送業の許可と言えば「緑ナンバー」「黒ナンバー」になります。霊柩車も例に漏れません。
- 緑ナンバーはどうやってもらえる?
- 軽自動車でも霊柩車出来るの?
- 車は何台も必要なの?
一般貨物、つまりトラック運送については5台以上用意する必要があり、資金は2000万前後必要と言われています。
霊柩車も同じでしょうか?専門の行政書士が徹底解説させていただきます。
この記事を最後まで読むと、霊柩車事業を始めるのに何を用意すれば良いかがわかります。
自動車・運送業手続行政書士髙橋です。自動車手続きは大阪・運送業支援は近畿二府四県対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「霊柩車許可支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。
霊柩車とは
他人から依頼を受けて、お金をもらってご遺体を運ぶことを許された事業になります。
これには「一般貨物自動車運送事業(霊柩限定)」という許可が必要になり、許可を得た自動車のナンバープレートは緑色・黒色になります。
自動車のナンバープレートは大きくわけて次の4つの色に分類されます。
白:自家用普通自動車
黄:自家用軽自動車
緑:事業用普通自動車
黒:事業用軽自動車
自家用は家庭や企業でただ乗るために使う場合や、自社の荷物を運ぶ場合は自家用です。
事業用はお客さんや他人の荷物をお金をもらって運ぶための許可を得ている自動車につけられます。これがいわゆる「運送事業」です。
代表的なところで運送屋さんのトラックやタクシーは緑ナンバーになります。
霊柩車も例に漏れず緑色ナンバーになります、ご遺体は貨物扱いになりますので貨物運送事業になります。
葬儀に必要な霊柩車と寝台車の違い
病院などでお亡くなりになられた方の輸送については、下記のようになります。
病院には礼儀上や縁起上でも霊柩車が来ることはありません。
病院からご自宅や葬儀会場などには「寝台車」と呼ばれるストレッチャーなどの設備が使える車両が使われます。
その後、葬儀を済ませ火葬場への搬送については皆さんがイメージする霊柩車で搬送されます。
霊柩車の正式名称は「一般貨物自動車運送事業」
前述しました通り、霊柩車は「一般貨物自動車運送事業(霊柩限定)」という許可が必要です。
この許可をするには
人員面
- 運転手
- 運行管理者
- 整備管理者
設備面
- 営業所
- 休憩所
- 車庫
- 営業車
資金面
- これらを用意して1年維持出来る資金の合計額を上回る預金残高。
上記が必要になります。
霊柩車は貨物運送の特例限定許可
通常の一般貨物がトラック5台以上が条件なのに対し、霊柩車の場合は1台から許可が下ります。
つまり自動車1台分、車庫も1台分、運転手も1名でOKになりますので、開業のハードルはかなり下がります。
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「霊柩車許可支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。
霊柩車と寝台車は同じ許可形態
寝台車も霊柩車も同じ霊柩車限定許可で行えます。
依頼を受けてご遺体を運ぶという面で、全く同じことをしているので、特に新しい許可は必要ありません。
気をつけたいのは霊柩車の車両で病院に行くことは縁起上も設備上も有りえません。
寝台車はストレッチャーなどの設備が乗るような車両が使用されるのが一般的です。
この場合、寝台用と霊柩用の車両が2台必要になります。
ですが初っ端から2台で許可を取ろうとすると資金面がタイトになりますので、導入のタイミングは予算次第では工夫が必要になります。
白ナンバーでご遺体を運ぶのは原則禁止
白ナンバーの自動車でできることの限界は下記の通りです。
- お客様の自宅へ自社の製品などの荷物を届ける
- 自社のお客様を自社に連れて行く
- お客様を自社からご自宅へお送りする
これ以上のことは白ナンバーの自動車ではすることが出来ません。
病院←→葬儀会場
葬儀会場←→火葬場
上記の例で、葬儀会場=自社だとしても、病院や火葬場には白ナンバーでは行くことができません。
ちゃんと霊柩運送を業として行いたい場合は、必ず許可を取らなければなりません。
霊柩車にご遺族の方を乗せても良い?
霊柩車はあくまで貨物運送になりますが、特殊な貨物の付添人として遺族を乗せる事が出来ます。
国交省から出ている「標準霊きゅう運送約款」では下記のようになっています。
(付添人)
第十条 当店は、依頼を受けた遺体の運送について、付添人の同乗を要求することがあります。
付添人としてご遺族の方を乗せることを前提に標準約款が作られています。つまり別途旅客運送の許可などは必要ありません。
霊柩車は軽自動車でも出来る?
霊柩車は軽自動車でも事業を行うことが出来ます。
軽自動車で行う場合は「一般貨物自動車運送事業」ではなく「貨物軽自動車運送事業」という別形態の許可(届出)になります。
貨物軽自動車運送事業は元々1台で始められます。ただし、一般と霊柩の車両の台数の明細を届けるので、霊柩車両で一般の荷物を運ぶことは出来ません。
霊柩については霊柩専用車両になります。
なお、軽自動車の霊柩車も存在します。外見は普通の軽バンですが、内部は霊柩設備になっている物が多いようです。
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について詳しくはコチラ
霊柩車許可取得のフローチャート
下記の準備や手続きを行い、許可を得てナンバープレートを付け替えます。
申請から許可まで数ヶ月かかりますので、準備から運輸開始まで早くて半年強かかると見ておいて下さい。
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「霊柩車許可支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。
霊柩車の取得条件
霊柩車の許可を得るには、運輸局が出しているヒト・モノ・カネの条件を準備する必要があります。
霊柩車に必要な人員
- 運転手(普通免許所持者)
- 運行管理者(資格等必要なし)
- 整備管理者(資格等必要なし)
大概の霊柩車や寝台車は普通免許で運転出来ますので、中大型の免許までは求められません。旅客でもないので二種免許も必要ありません。
霊柩車・寝台車合わせて4台までであれば「運行管理者」「整備管理者」は資格が必要ありません。どなたでもなることが出来ます。
ただし「運行管理者」と「運転者」は兼任が出来ませんので、車1台で始める場合でも最低2名の人員が必要になります。
霊柩車に必要な施設や設備
- 営業所
- 休憩所
- 車庫
- 霊柩車1台以上
各施設や設備には細かい決まりがあります。
車庫は農地などでなければ大体の所に設置できますが、営業所は設置できない地域が少なくなく、これに引っかかる事業者さんも多いです。
借りたり買ったりする前に綿密な調査が必要になります。
営業車は、車検証上の用途が「特殊」車体の形状が「霊柩車」になっている自動車が使用されます。
霊柩車の営業エリア
霊柩車の営業エリアは都道府県単位になり、営業所は営業エリアになくてはならないです。
トラック運送は営業エリアがなく全国いけますが、4台以下の霊柩車は営業エリアのある都道府県でしか営業が出来ません。
大阪で許可を取った場合
- 大阪で乗せる→他県で下ろす
- 他県で乗せる→大阪で下ろす
上記はOKです。
・他県で乗せる→他県で下ろす
上記はNGです。
なお、この縛りは5台以上になった時になくなり、全国で活動できるようになります。
霊柩車取得に必要な資金
目安は自動車台+350万前後が銀行口座に入っていれば大丈夫かと言った所です。
銀行口座は必ず必要です。近年、新設法人に口座を開かせてくれる金融機関は少ないのでご注意下さい。
- 人件費半年分
- 家賃1年分
- 任意保険1年分
- 車両購入代金またはリース料金1年分
これらを合算して資金計画を作ります。
- 資金の1年分の半分
- 開始2ヶ月で必要な資金の全額
これのどちらかの高い方を銀行の残高が上回っていれば資金計画はクリアです。
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「霊柩車許可支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。
霊柩車取得のための申請書作成
ヒト・モノ・カネの要件が揃えられたら、それに沿って申請書を作成します。
申請書は分厚さ1センチ程度の書類の束になり、ファイルで綴て運輸局に提出します。
書類が苦手な方はこれを聞いてゾッとすると思いますが、その場合は専門家に依頼することをお勧めします。
申請書につける必要添付書類
申請書は書くだけになりますが、申請書に書いた事が正しいと証明する添付書類が必要になります。
- 任意保険見積書
- 自動車の見積書
- 賃貸借契約書
- 資格者証や免許証
主にこの辺りを集めて貰うことになります。
見積書を各所から取って頂き、それを計算して資金計画を算出します。
申請書、添付書類をすべて提出し、法令試験に受かると書類審査が始まります。
運送業許可後・運輸開始届までの準備
書類審査が終わり、要件が整っていることが確認できれば許可が下ります。
許可についてはすべて見積もりで通りますので、許可後はそれらを本契約にして運輸開始準備を整えていきます。
- プレートの付替え
- 施設の賃貸借本契約
- 自動車の購入
- 任意保険の本契約
上記の準備が整い次第、運輸を開始して頂いてOKです。
運輸開始後「運輸開始届」を届け出ます。これは事後届でOKですが、出さないと増車や変更などが出来ませんので忘れずに出すようにして下さい。
弊所ご依頼頂きました場合、新規許可から運輸開始届までの半年間、密にお付き合いさせていただきます。
ご依頼の場合、下記ボタンで弊所を友だち追加後「霊柩車許可支援無料相談」とご一報頂きましたら、ご訪問やWeb会議、お電話での相談日設定させていただきます。
霊柩車の増車手続き
増車をしたい場合などは、運輸局で手続きを行い、緑ナンバーを新たに貰わなければなりません。
運輸開始後も何かを変える場合は運輸局で手続きが必要になります。下記はその一例です。
- 営業所の住所
- 車庫の位置
- 車庫の大きさ
- 自動車の台数
増車をしたい、だが車庫が小さいという場合はまず車庫を大きくする手続きが必要です。
車庫の拡大は、事業の拡大という扱いになり、事業計画変更の認可が必要です。認可は2ヶ月程度かかりますので、すぐには増やせない事を考慮する必要があります。
営業所についても、新規の時と同じ要件がありますので、賃貸借契約書や図面、写真などを確認の上で審査されます。
霊柩車の増減車届け
車庫が既に大きく、車を増やす余裕がある場合は、増車は届け出だけでOKです。
逆に減らす事についても届け出だけでOKです。ただし、5台以下にならないように注意して下さい。
5台以下にならないように、減車と同時に増車を持って行くなどしなければなりません。
増減車を届け出て受理された後、別途自動車の番号変更登録、プレートの付替えも必要になります。
霊柩車にもトラック協会から巡回指導が来る
霊柩車も貨物運送になりますので、例外なくトラック協会から定期的に巡回指導が来ます。
霊柩車なのでトラック協会とはあまり縁がないですが、巡回指導はトラック協会が請け負っていますので下記のタイミングで定期巡回に来ます。
- 第一回:許可後3ヶ月以内
- 第二回以降:3年に一回
- 巡回の結果が悪かったら:半年後
38項目のチェックを受けて、ABCDEのスコアを付けられます。DE評価の場合改善の報告が求められ、次回の巡回指導が半年後になります。
帳票や人員の体制などをしっかりしておかないと評価が下がりますので、それ相応の準備が必要です。
霊柩車の許可の更新
2025年6月に法案が可決し、トラック緑ナンバーも更新制が導入されることになりました。霊柩車も例に漏れず更新許可を5年に一度取る必要が出てきました。
2026年1月施行、3年の猶予期間の後5年更新制になるとのことです、つまり更新許可を取らないと事業が継続できなくなります。
更新許可にも審査がありますので、更新が出来るような体制を整える必要が今後出てきます。
更新許可の審査内容については詳細発表次第、当HPでも共有させていただきます。
まとめ
- 霊柩車を始めるにはまず運送業許可が必要
- 許可取得には条件に合った準備物が必要
- 許可取得には書類を集めて申請が必要
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡で「緑ナンバー取得支援相談」と明記しご連絡お願いします。納期についてご相談させて頂きます。
行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212
TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
営業時間:9:00~20:00 ※土日祝お電話受け付けております